生ごみのリサイクル情報(堆肥作りに挑戦しませんか)
(注意)家庭用コンポスター等を使用する際は、虫や臭いの発生により近隣の住民に迷惑をかけることが無いよう、正しい使用方法を確認し、適正にご使用いただくようご注意願います。
捨てるのもったいない 生ごみだって立派な資源です!
堆肥作りに挑戦してみませんか!
自分の家から出る生ごみだから安心ですよね
おいしい野菜が収穫出来て、きれいな花が咲いたらなおさらウレシイ♪
自分にあった方法はどれかな?
電動生ごみ処理機

あまり手間はかけず手軽に室内で堆肥を作りたい人に
コンポスター

家族が多く、生ごみも結構出る。堆肥がたくさん欲しい人に
密閉式容器

小バエが発生する心配もなく室内で堆肥を作りたい人に
ダンボール堆肥

あまり経費をかけず手軽に室内で堆肥を作りたい人に
電動生ごみ処理機で堆肥作り


電動生ごみ処理機は、電気を使用して減量・堆肥化するための機械です。
種類は3種類
高温の温風で生ごみを乾燥処理する乾燥型と、微生物に生ごみを分解させるバイオ型、また2つの特徴を合わせたハイブリッド型といわれるものがあります。
乾燥型
高温の温風で生ごみを乾燥する方法で、最近は運転中の嫌なニオイがほとんどしないということです。
堆肥として使用するためには、発酵のため約1ヵ月半の間、土に埋め、土の中の微生物に分解させる必要があるようです。
基本的に電気代以外はかかりません。
バイオ型
バイオチップを用い、電気で温めた機械の中で微生物の活性化を促し、生ごみを処理する方法で、運転中は腐葉土のようなニオイがすることがあります。
処理物については、微生物の力で、すでに1次発酵が終わっているので比較的すぐに堆肥として使用することが出来ます。
電気代のほかに培養基材(バイオチップ)代がかかります。
ハイブリッド型
生ごみを送風乾燥してから微生物で分解処理する方法で、乾燥型とバイオ型の両方の長所を生かしたものです。
バイオ型と同じく腐葉土のようなニオイがすることがあります。
処理物は堆肥として使用することが出来ます。
基本的に電気代以外はかかりません。
(注意)詳しくは製品の仕様書をご覧になるか、販売店やメーカーにお問い合わせください。
ポイント
- 処理機の能力以上の生ごみを投入すると、臭い発生の原因となるので注意しましょう
- しっかり水を切ってから入れると、電気代を節約できます。また、できるだけ細かくきざむことも大切。
コンポスターで堆肥作り

バケツを大きくしたようなプラスチック製の容器を使う方法で、土中の微生物(バクテリア)の働きで生ごみを堆肥化するものです。
用意するもの

- コンポスター容器…100~200リットルのものがあります。生ごみの量に合ったものを選びましょう。金物店・ホームセンターなどで購入できます。
- 発酵促進剤または米ぬか
- スコップ
1.コンポスターを設置する
なるべく日当たりの良い土の上に設置し、深さ20~30センチメートルの穴を掘ります。排水をよくするため、中心部をさらに20~30センチメートル掘り、コンポスターを設置し、周囲に盛土をして足で踏み固めます。
2.床を作る
底に枯れ葉、枯れ草を敷いて床を作る。(米ぬかがあれば3センチメートルくらい入れてから、枯れ葉、枯れ草を入れるとより微生物の活動が活発になり、発酵が促進されます)
3.生ごみを入れる
新鮮なうちによく水を切った生ごみを細かくしてコンポスターに入れます。コンポスター内の生ごみがべとべとしているときは、乾燥した土や枯れ葉、枯れ草を生ごみの半分の量全体を覆うようにふりかけます。発酵状態が良い場合は必要ありません。天気のよい日にはフタを開けて、風と太陽の光をいっぱい入れる(網をかぶせるなどして虫の侵入に注意すること)。これを繰り返し、いっぱいになったら1ヶ月以上放置しておきます。
4.堆肥として使う
コンポスターを取り外し、処理した生ごみを土と混ぜておくと1ヶ月くらいで良い堆肥が出来上がります。プランターでは、土10リットルに対して2・3割混ぜてください。
ポイント
スイカやメロンなど特に水分の多いものは刻んで入れましょう。
堆肥が完熟してくると材料にかかわらず色が黒くなってカビくさい感じです。強いアンモニア臭がする場合は、成熟が不十分です。ウジ虫などが発生した場合は、石灰を入れると効果があります。また、発酵促進剤を入れると臭いや虫が発生しづらくなります。
悪臭が発生する場合は、水切り不足や、臭いが発生しやすい品目(肉、魚、柑橘類の皮等)を混入させている可能性や、使用方法を誤っている可能性があります。メーカーのホームページなどで、正しい使用方法を確認し、適正にご使用いただくようご注意願います。
密閉式容器で堆肥作り

密閉式の容器を使うため、虫が発生しづらいのが特徴で、屋内でもできるため、冬でも続けることができます。
用意するもの

- 密閉式容器(10~20リットル程度)
底が2重になっていて、水抜きのコックがついたものが便利です。(金物店・ホームセンターなどで購入できます。) - ボカシ(4人家族で1ヶ月に2~3キログラム必要)
(注意)ボカシとは…米ぬかやもみ殻などをEM菌(有効微生物群)と混ぜ合わせたもの。 - シャベルやしゃもじ
- 新聞紙1枚
- 生ごみ
| 処理できるもの |
野菜くず、卵の殻などの調理くず ご飯、パン、おかずなどの残り物 魚の骨、頭、内臓など |
|---|---|
| 処理できるが 入れないほうが良いもの |
枯れた草花など 鶏、豚、牛などの骨や貝殻など 印刷されていない紙屑、厚紙、段ボールなど |
| 処理できないもの |
腐った生ごみ タバコの吸い殻 プラスチック類 |
堆肥の作り方
1. 新聞紙を入れる
容器の汚れを防ぐために、新聞紙を4枚に切り、容器の底に1枚、側面に3枚入れる。
2. ボカシを入れる
指先ひとつかみ(10グラムほど)のボカシをさっとまきます。
3. 生ごみを入れる
新鮮なうちによく水を切った生ごみを容器に入れ、500グラムに対しボカシをひと握り分(20~30グラム)ふりかける。
4. 混ぜる
しゃもじなどを使って、軽く混ぜて、生ごみを上から押さえ、生ごみの間にある空気を押し出す。中ふたをして、きっちりと上フタをする。
5. 毎日の管理
毎日、手順3、4を繰り返します。
発酵が進むと、容器の底に発酵液が溜まってくるので、こまめに取り出します。
発酵液の利用方法

発酵液は、水で1,000~2,000倍に薄めて肥料として使えます。週1回程度散布してください。ただし、空気に触れると悪臭が発生しやすいので早めに使うようにしましょう。
6. 直射日光のあたらないところに置く
容器が一杯になった後、10日ほど発酵させると悪臭のない肥料ができます。ぬか漬のような匂いになれば成功です。
7. 堆肥として使う
畑や菜園の畝間にすき込む。また、プランターの土に混ぜ込む(土3に対してボカシ和え1の割合)
冬期はごみ袋や漬物容器などに入れ、倉庫などで保管。
ポイント
- 生ごみはできるだけ細かくしておくと、微生物が働きやすくなります。
- ボカシは惜しまずに入れる。特に夏場は多めに入れる。
- ガスの発生でフタがとれないことがあります。
- この方法は、空気のない状態で働く微生物の活動を利用したものなので、しっかり密閉する。
詳しい内容は、取り扱い説明書を御覧下さい。
ダンボール箱で堆肥作り

用意するもの
- ピートモス(6リットル)
- もみがらくんたん(4リットル)
金物店・ホームセンターなどで購入できます - ダンボール箱
10キログラムのみかん箱くらいの大きさ - 棒温度計
- ダンボール製のフタ
- かくはん用のこて
シャベルやしゃもじなど - ダンボール箱の土台
木片等、ダンボール箱の底の通気を保てるもの
堆肥の作り方

| 1 | ダンボール箱に、ピートモス・もみがらくんたん(6対4の割合) を混ぜたものを半分程度くらい入れる。 |
| 2 | その中に、生ごみを水を切らずに入れてよくかくはんする。 (最初は生ごみの量を多めに~1キログラム程度) |
| 3 | 温度計を中心に差し、フタをする。 |
| 4 | 室温が15℃以上の場所に設置する。 |
| 5 | 生ゴミの投入とかくはんを繰り返し、3~4ヶ月を目安に黒土と混ぜ、さらに1ヶ月間そのまま寝かせると堆肥が出来上がる。 |
Q&A
1.温度

なかなか温度が上がらないが、どうしたらよいのか?

- 温度が上がらないときは、使用済み天ぷら油、きな粉(いずれも100グラム程度)などを入れるとよい。
- 肉や魚を多く入れると、分解が早まり温度が上昇しやすい。
- 野菜くずなどがほとんどであれば、ゆっくり分解し、温度はそれほど上がりません。
3.臭い

臭いは出ないのか、出たときはどうしたらよいのか?

- 1回に入れる生ごみの量が多いと、容器内の温度が急激に上昇し、カビ臭や土の臭いが出ます。
- イカごろなどを入れると、アンモニア臭がきつくなります。
- 臭いが我慢できなければ換気の良い所に移すなどして、1~2日置くとおさまります。
- 防ぐ方法としては、1回に入れる生ごみの量が多くならないように調整するとよい。
3.カビ、虫

虫などは発生しないのか?

- 基材の表面に白カビが生える場合があります。(好気性菌で無害)
- 小ばえ、ダニが発生することがあります。
- 生ごみ投入を4~5日停止したり、かくはんをしないで放置すると発生しやすくなります。
- あまり日を空けないで生ごみを投入し、よくかくはんするようにしてください。
4.使用期間後の使途

基材の使用期間はどのくらいか、また、終了後はどうしたらいいのか?

- 基材の使用期間については、投入した生ごみの量によって違いがあり、一概に言えませんが、生ごみ投入量が平均500グラム/日であれば3~4ヶ月くらいを目安にしてください。
- 基材は、黒土と混ぜて1ヶ月程度寝かせて堆肥として使用することが出来ます。
- 次の処理セットのために、使用済みの基材(細かい部分)を少し残し、新規の基材と混ぜて使用すると、新規の時より温度の上昇時期が早まります。
5.その他
上記2・3の防止策として、あるいは分解を早く進めるには、「かくはん」をしっかりするとよい。
生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課
電話 :0123-33-3131(内線:1131・1132)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
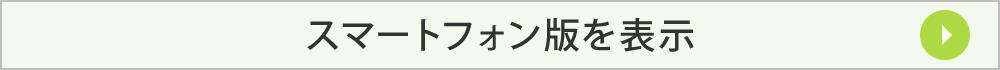








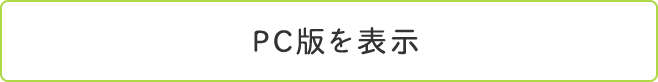

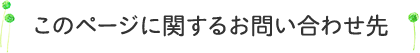
更新日:2021年07月21日