障害児通所支援事業の利用について
1.障害児通所支援事業とは
障がいや発達に心配がある児童の発達支援を行う児童福祉法に基づく事業です。
| 児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作、知識技能の習得、集団生活への適応のために必要な支援を行います。未就学児が対象です。 |
| 放課後等デイサービス | 生活能力の向上、社会との交流の促進のために必要な支援を行います。就学児が対象で(幼稚園、大学を除く)、授業の終了後または休業日に支援を行います。 |
| 保育所等訪問支援 | 日常通っている保育所、幼稚園、小・中学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がいがあり、児童発達支援または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作や生活能力向上のために必要な支援を行います。 |
2.対象児童について
対象児童であることを確認する必要があるため、以下のいずれかの書類等をご用意ください。
1.障害者手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)を有する児童。
2.特別児童扶養手当を受給している児童。
3.上記以外で何らかの支援が必要な児童。
3.利用開始までの流れ
事業を利用するためには、通所受給者証が必要となります。交付のためには、えにわっこ応援センターに必要書類を揃えて申請していただきます。
【利用までの流れ】
| 1 |
えにわっこ応援センターまたは障害児相談支援事業所に相談します。 |
| 2 |
えにわっこ応援センターで申請書類一式と障害児支援利用計画案提出依頼書をお渡しします。 |
| 3 |
障害児支援利用計画の作成にあたり、相談支援事業所と契約を交わします。 |
| 4 |
相談支援事業所が利用計画(案)を作成します。 |
| 5 |
えにわっこ応援センターに必要書類を提出します。 ※「申請に必要な書類」を参照してください。 |
| 6 |
書類の提出時に、介助の必要性や障害の程度の把握のための調査、利用予定の事業所の確認、添付書類の内容、利用計画(案)の内容等、支給の要否を決定するために必要な事項の聞き取りを行います。 |
| 7 |
えにわっこ応援センターから受給者証を交付します。 |
| 8 |
相談支援事業所が利用計画(本計画)を作成します。 |
| 9 |
希望する通所支援事業所と利用契約を交わします。 |
| 10 |
サービスの利用を開始します。 |
| 11 |
相談支援事業所がモニタリングを行います。 |
4.申請に必要な書類
1.申請書(下記の添付ファイルから印刷してご利用ください。)
2.障害児相談支援利用計画(案)
3.対象児童であることを確認できる書類の写し
手帳、手当証書、診断書、意見書等
4.マイナンバーカード(申請者、対象児童等)など、個人番号の分かるもの。
5.利用者負担額
毎月の利用総額の1割が利用者負担となりますが、世帯の収入状況に応じて1ヶ月あたりの上限額(上限負担月額)を設定します。この上限額以上はかかりませんが、事業所によっては「おやつ代」等の実費負担が発生する場合があります。
| 区分 | 世帯の所得などの状況 | 負担上限月額 | |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
| 低所得1 | 市民税非課税世帯 |
障害児の保護者の収入が 年80万円以下 |
0円 |
| 低所得2 | 市民税非課税世帯 | 低所得1に該当しないもの |
0円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯 | 所得割28万円未満 |
4,600円 |
| 一般2 | 市民税課税世帯 | 上記以外 |
37,200円 |
無償化
満3歳になった年度の翌年度の4月1日から開始し、小学校就学前までの3年間、障害児通所支援等の利用者負担額が無償化されます。
多子軽減制度
市民税課税世帯のうち、第2子以降の未就学児にかかる障害児通所支援の利用者負担額の軽減を行う制度です。世帯における市民税所得割合計額によって条件が異なります。
恵庭市内の障害児通所支援事業所一覧
恵庭市内の障害児通所支援事業所一覧 (PDFファイル: 47.1KB)
恵庭市内の障害児相談支援事業所一覧
子ども未来部 えにわっこ応援センター
児童福祉担当
電話 :0123-33-3131(内線1241)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
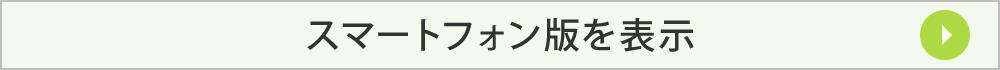








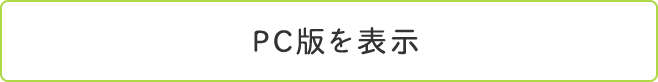

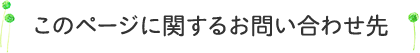
更新日:2024年10月03日