第1回行政改革推進委員会-平成28年5月27日
平成28年度第1回 恵庭市行政改革推進委員会 会議録(概要)
1 日時
平成28年5月27日(金曜日)10時~12時
2 会場
市民会館2階 中会議室
3 出席者
- 委員:横山委員長、鶴田委員、冨成委員、野呂委員、藤井委員(欠席;高野副委員長、内山委員、今野委員、池田委員、森田委員)
- 北越副市長
- 事務局:後藤企画振興部長、大槻企画振興部次長、溝企画・広報課長、 井上財政課主幹、吉田企画・広報課主査、瀬川企画・広報課主任
4 内容
(1)平成27年度行政評価の結果に伴う報告について
平成27年度行政評価の結果に伴う各所管課の今後の取組について事務局から報告
質疑応答
子どもひろば事業について
質問:<A委員>子ども広場事業というのは子育て支援センター柏陽、島松、黄金の3箇所で実施している事業なのか。
回答:子ども広場事業を子育て支援センター活用して実施している場所もあるが、巡回ひろばという事業があり、市内施設を巡回して実施している部分もある。
参考事例
三鷹市の子育て支援の取組について(横山委員長より紹介)
市の姿勢次第というか市の政策方針次第ではあるが、今子育てをどうするかというのは国にとっても大変に大きな問題で、国も色々と取組を行っているところだが、保育所待機者問題が非常に注目をされている。ただ現実的に考えると、働く母親の問題っていうのも保育所の問題だけれども、家庭にいる母親も結構多く、ずっと家庭の中にいる母親というのは色んなストレスを感じてくるわけである。そういう面で言うと自治体によっては子育て支援センターをものすごく重要視して、広場事業などと相談事業を合わせるような形で対応しているところもある。子供を遊ばせながら相談をするという仕組みをつくったりしているところもある。福祉関係から医療関係、色んなネットワークを作らなければならないと思う。そういうことを自治体としてやっていく気があるのであれば、すぐに民間委託ということではなくて、まず自治体がしっかりと対応していくというやり方もあるのではないかと思う。
そこで三鷹市の事例を挙げると、1990年代に直営で子育て支援センターを始めたわけだが、ネットワークが非常に良くて子供を遊ばせながら相談した時に、保育士では対応できない問題がいっぱいあり、虐待の問題だとか医療の問題、そこに児童相談所の職員や医者がその子育て支援センターに来て相談を受ける仕組みをつくった。ネットワーク形成をしていくと非常に政策効果があると思う。それ自体は直営でやっているが、あとはそれぞれ民間の方達やそこの地域の人達を活用していくような仕組みである。
他市の調査をするのであれば是非、三鷹市の優れたところを見て、恵庭に置き換えて検討するような調査を行えばよいのではないか。今子育ての問題はすごく重要で、それに自治体がしっかり対応できるようにするということが大事だと思うので考えていただければと思う。
こういうソフトな政策を一回煮詰めていくというか民間のネットワークをつくっていくと、すごく優れたまちづくりになるのではないのかと私は思っている。
恵庭市の待機児童の状況について
質問:<A委員>保育所にはどれくらい待機児童がいるのか。
回答:公表している一般的な待機児童はゼロ。ただし、潜在的に「子供を預かってくれれば働きたい。」と感じている方がいるのではないかと考えられる。
市民スキー場維持管理事業
質問:<E委員>市民スキー場の整備とかあるが、本当に恵庭として持っている必要あるのか。
回答:利用者数は決して多くはないが学校で使っている状況がある。効率の問題からすると、たった数回の学校の為に残すのかという問題もあるのだが、恵庭市内の小学校はスケートとスキーのどちらかを選べるようになっている。スケート場も存続の問題があってスケート場へ行って授業を行うのと、自分の学校にスケート場を造って授業を行う場合の経費や時間の問題等色々と検討をしているところがあり教育委員会で相当悩んでいる。今後の問題として取組んでいきたい。
駅自由通路維持管理事業
質問:<E委員>駅の自由通路の維持管理事業について、夜間の照明代など維持管理費がかかるが夜間に自由通路を通る人はどれだけいるのだろうか。夜間は全部通行止めにしても差し障りもないのではないか。
回答:自由通路の維持費は多分年間1億以上かかっており、見直そうということから、内部では夜間の通行止めも検討したが、自由通路は市道であり公道あることから24時間通行できるようにしている。
ただし。経費的に効率性の検討を行い、清掃・保守などの委託について一括で発注することとしている。
ただし。経費的に効率性の検討を行い、清掃・保守などの委託について一括で発注することとしている。
わくわくおたから市事業
質問:<E委員>わくわくおたから市という事業も行政で行わなくて良いのではないか。見直しより廃止してもいいのではないか。
回答:わくわくおたから市について本年度より回数を削減する予定である。
移住促進事業
質問:<A委員>移住促進事業の成果について、移住の実績人数はどうなっているのか。
回答:以前、子育て世帯バスツアーに参加された方へ照会すると、恵庭に住んでいますと回答された方がいた。バスツアーでは、新たな住宅地を照会しており、そのようなことをきっかけに引っ越した方がいると聞いている。
札幌恵庭自転車道線整備促進事業(自転車散歩)
質問:<B委員>自転車道の民間委託をどのように進めていこうとしているのか。
回答:事業内容は自転車イベントのことである。イベントを外部に委託しようと考えている。
質問:<B委員>札幌恵庭自転車道の計画で恵庭までの自転車道延伸のルートは決まっているのか。
回答:ほぼルートは決定しており、これから設計や測量にかかるということで進んでいる。詳細については関係機関により技術的問題などを詰めているところである。
質問:<E委員>ルートとして街中を通るのは現実的ではないのではないか。
回答:車両があまり通らない河川敷などをルートに入れて考えている。街中といっても、ある程度は恵庭市らしさを入れて決定したいと考えている。
市民活動推進事業(えにわ市民プラザ・アイル事業費補助金)
質問:<B委員>今年から運営費補助から事業に対する支出をしているようだが内容などはどうなっているのか。
回答:高齢者や障がい者、留守家庭の支援などの事業化を考えている。
質問:<A委員>事業の今後の展開はどう考えているのか。
回答:やはりこれは人的問題であり、人数的なものや専門的な人員がいるのかどうかが課題になるかと思われる。
(2)平成28年度における行政改革推進方針及び取組について
「平成28年度における行政改革推進方針及び取組について」事務局から説明
質疑応答
行政評価について
質問:<C委員>72事業をベースに専門部会評価対象にするということだが、平成27年度評価の事業も含まれているのか。
回答:含まれていない。平成24,25,26年度である。これらを行政評価マニュアルの取扱いに従って進捗管理する。
PPPの推進について
質問:<E委員>様々な事業に対して民間委託や指定管理を導入するというのは、ノウハウを確立しないと進まないと思う。検討しても民間の利益の部分の話となり難しいとは思うが、そこは頑張っていただければと思っている。
回答:指定管理者制度は現在13件の実績がある。やはり事業者側で、収益がでるような取り組みが必要あり、それをできるような裁量権を与える必要があるため、このような点はこれからの課題だと思っている。
質問:<C委員>恵庭水泳プール8カ所とあるが学校のプールか。
回答:市内小学校8校のプール。
質問:<D委員>指定管理者のなかで、採算性が悪くてサービスが低下しているとか、情報を集約しているとか現在の実績を捉えているのか。
回答:指定管理者ごとに、毎年モニタリング調査として実施状況の報告、支出の関係、市民アンケートを行っている、苦情の状況などは全てモニタリング会議でおさえており、評価をしてきているところ。ただ形骸的になり始めているため、もう一度モニタリング制度のあり方を改めていきたいと考えている。制度を導入し10年経過したため見直しを行う。
公共施設マネジメントについて
質問:<A委員>基本方針はできていて、これからは具体的な話に入っていくのか。
回答:今年の2月に基本計画をお示しした。今年度は実施計画の策定に入る。
当面の10年間では基本的には住民サービスに1番影響のない部分である行政が使っている施設から減らす。その後、市民サービスの中でも、利用者が限定されており利用少ない施設や老朽化が著しい施設等を見直す対象と考えている。
学校の耐震化について
質問:<C委員>学校の耐震化というのは、ほとんど終わったのか。
回答:終了している。ただし、非構造部材の耐震化については今年度完了予定。
公共施設総合管理基本計画の見直し時期について
質問:<E委員>公共施設総合管理基本計画は30年という長い計画だが、計画途中での見直し時期は決まっているのか。見直しには民間の人も入れてはどうか。
回答:これから10年ごとに実施計画を立てていくが、意見もあったとおり民間の方、市民の意見を取り入れるような見直しも考えられるため、そうした中で進めていきたい。
質問:<E委員>10年というのは随分長い。もっと短いスパンで見直していかないと現状に合わなくなるのではないか
回答:全体として30年で11%削減する予定である。10年だと例えば4%削減となると、28万平方メートルの4%だから1万平方メートルの削減。1万平方メートルを減らすとなると相当に大変であり、途中途中で必ずしも市民の意見を入れるとなると、逆にできなくなる場合もでてくる可能性がある。
質問:<E委員>逆に行政だけで見直すというよりも、そういうところを英断してくれる外からの目というのがあるといいと思うのだが。
回答:できれば、行革委員会の皆様より民間的な視点で厳しくご意見をいただければと考えている。 人口、税収の問題があり、今ある施設が維持できなくなった場合にどうするかという切実な問題であるため理解いただいき、「多少距離は遠くなっても機能としては残ります。」ということを時間かけて調整する必要があると考えている。
(3)まちづくり基本条例の検証について
「まちづくり基本条例の検証について」事務局から説明。
質疑応答
<A委員>私もこのまちづくり基本条例にずっと関わってきた。実際に色々な自治体に関わってきたが、条例に書いている割に検証を進めてない自治体は多い。恵庭の場合は3年目で既にこういう準備を始めたということは非常に良いことだと思う。
是非、行政の調査を行なっていただき、5年目でいいと思うが、見直しのための検討委員会を立ち上げる必要があるのではないかなと思う。
恵庭は条例を見直す必要があるかどうか、検討してみなければ判らないが運用の面でもう少し工夫したらいいのではという意見がでてくるかも知れない。是非、行政の方で検討調査されて、その後、市民検討委員会をやっていただければと思っている。
市民も行政職員もすごく一生懸命に策定した「まちづくり条例」というのが恵庭の特徴ではないかと思う。
恵庭市民憲章について
<B委員>まちづくり基本条例とは違うのだが、恵庭市民憲章ができてから40数年経っているが、市民まで浸透していないのではないか。
<A委員>逆に言うとまちづくり条例を策定し、そこにこの市民憲章という言葉を入れることによって、少しまた周知できるのではないかというのもあった。
<C委員>色々な会議があるが、市民憲章が読まれることもある。今読んでも素晴らしい言葉。40数年前に書かれたものが現在も活きているという感じで大変良いと思う。
まちづくり基本条例の周知度について
質問:<E委員>恵庭市まちづくり基本条例の周知度について行政はどう思っているか。
回答:<A委員>条例の策定については、町内会の人を集めるなど色々取組みなどを行ったが、条例ができてすぐにみんなに周知できるとは全然考えていなかった、最初は1割でいいのではないかというくらいの感覚であり、徐々に徐々に浸透していくということであって、これからだと思う。
<課長>第5期総合計画では、政策ごとに成果指標、目標を定めている。
市民協働についても大きな柱としており、その成果指標として「まちづくり基本条例の認知度の向上」としている。市民の方へアンケートを行い、認知度として26年度末で55%の方が知っていると回答された。条文は知らなくても、基本条例があるというは、かなり浸透しているのかも知れない。
5.その他
次回、委員会を8月末か9月の初めの方に開催を予定している。今後ともご協力お願いいたします。
以上
企画振興部 企画課
電話 :0123-33-3131(内線:2341)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
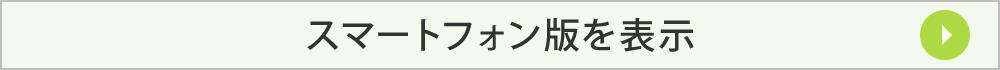








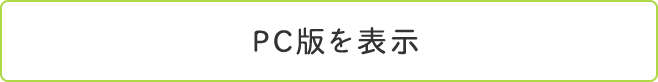

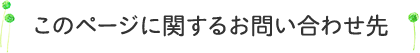
更新日:2019年03月29日