行政改革推進委員会-平成27年7月7日
平成27年度第1回 恵庭市行政改革推進委員会 会議録(概要版)
1 日時
平成27年7月7日(水曜日)14時~16時30分
2 会場
市役所 3階 301・302会議室
3 出席者
- 副委員長(佐々木委員)、委員(真藤、佐藤、林、藤井、雪下、結城、五宝)、欠席委員(銅道、宮)
- 事務局(企画振興部長後藤、企画振興部次長林、企画・広報課佐々木・瀬川)
4 議題
「第5次行政改革推進計画の総括について」
- 事務局説明(大槻課長)
- 議題資料を会議開催前に配布するとともに、事前に質疑事項の提出を願った。
当日は、事務局が提示した質疑事項の回答をもとに議論を行った。
主な質疑応答
質疑項目1.質疑事前報告方式について
(A委員) 事前質問形式をとるのではなく、会議の場で自由闊達な意見を踏まえながら会議を運営するのが望ましい。
(B委員) 会議の時間に限りがあるので、内容の濃い討論を行うためにはこの方式が良い。
(C委員) この場で話したほうが、もっと実態に沿った話が出来ると思う。
(D委員) この方式は、前回の会議で提案させていただいた。回答についても事前にいただければ、更に議論が増すと思う。
(E委員) この方式が効率的であるとともに、行政側にとっても事前に資料をそろえることができる。事前に質疑を出す・出さないは各委員の判断に委ねればよい。
(F委員) 質問に対して事前準備ができるという面で、この方式をとるのがよいと思う。できれば、回答も事前にいただければ、活き活きとした議論がさらにできることになると思う。
(事務局) 皆様に戸惑いを与えたことは申し訳なかったが、事前に質疑を出していただいたのは、こちら側としてもある程度の 準備をさせていただくことでより的確な回答を差し上げることができ、有意義な議論ができると考えたからである。いずれにしても、会議の場での質疑応答を妨げるものではないことはご理解願いたい。
(A委員) この方式のほうが効率はよいのであろうが、質疑の事前提出は委員の負担にもなる。そのことも十分留意してほしい。
(G委員) 行政との隔たりを感じている、もっと市民に近寄る姿勢で臨んでもらいたい。
質疑項目2.各項目の「マニュアル」のおさえに関して
(A委員) 様々なマニュアルをお持ちかと思うが、回答のとおり、広い視野をもっての市民対応を心がけてほしい。
(E委員) マニュアルの運用を通じ、常に見直しを行っていく、という姿勢が必要である。
(事務局) マニュアルの運用の見直しについて、職場内会議等を通じて、常に見直しの姿勢をとっていきたいと考えている。
質疑項目3.市民活動組織改組に関して
(注意)質疑なし
質疑項目4.人事制度基本計画推進
(C委員) 再任用制度はいつから始まったのか。
(事務局) 制度自体は平成20年度からだが、実際の運用は平成22年度からだったと思う。
(C委員) 再任用職員の給料はどれくらいか。また、仕事内容は現役職員と同じか。
(事務局) 管理職の再任用職員については現役の6割程度、その他の再任用職員については、月額15万円程度となっている。仕事内容は職に見合ったものとなっている。
(C委員) 天下り先をつくっているような印象を受ける。40代~50代の職員の空洞化を補うための制度であれば空洞化がなくなれば必要なくなるのではないか。一部の人たちの天下り先をつくるとそれが常態化するのでは、との懸念がある。
(事務局) 管理職の再任用は3年連続して同じポストにはつかない。実際のところは年金制度との兼ね合いがある。定年延長が議論されたことがあるが、近いうちにその議論はでてくることにはなると思う。
(G委員) 非常勤職員が増えている。職員と同様の仕事をしているのに給料が低い、となると、職務に対する姿勢がゆらぎ、個人情報漏えいなどのセキュリティの面で問題がでるのでは。給料体系の見直しが必要では。
(事務局) 子ども施策の拡大により、非常勤職員は確かに増員している。セキュリティの面では、正職員である・ないに関わらず、個人のモラルを問うべきだと考えている。
質疑事項5.議案の「総括」について
(注意)質疑なし
質疑事項6.第5次行革推進計画(総括)「2.計画の取り組み状況」について
(B委員) 取組みを進めていく中で課題は必ずあるはず、課題の記載について検討していただきたい。
(事務局) 検討したい。
質疑事項7.第5次行革推進計画(総括)「3.計画の全体総括」について
(B委員) 市民との協働、という計画の趣旨からいっても、「官民協力体制の整備については取組の遅れが見られ(議案資料 4ページ8行目)」という表現はどうか。
(事務局) ここでは、官民協力体制の整備が進まなかったことを記載しており、市民との協働についての取り組みの遅れを示しているものではないのでご理解願いたい。
(E委員) 市民との協働の部分で、確かに枠組みづくりはできたが、まだまだ課題はある、その部分も意識して総括してはどうか。
(事務局) 検討させていただきたい。
質疑事項8.「人事制度基本計画の推進」について
(A委員) 再任用管理職の役割は。
(事務局) 管理職としての職責に見合った仕事をしている。
(C委員) 再任用職員の手当について、住宅手当は支給しているのか。持ち家を持っている職員に住宅手当を支給しているのは納得がいかない。
(事務局) 再任用職員には住宅手当は支給していない。持ち家手当については2年後に廃止、現在は段階的に削減している。
質疑事項9.予算の5%シーリングについて
(B委員) 今年度予算で5%のシーリングを実施している。行革の成果としての削減額は653万円の削減、行革としてもう 少し削減額を出せないか。
(事務局) 平成26年度の行政評価の平成27年予算の反映額としてはその程度であるが、取組みが進めばもっと大きな額になる。 人口減少社会は生産年齢人口の減少ということになり、市にとってみれば税収の減となる。
その意味では、事務事業の見直しをもう少し切り込んで行う必要があり、多少時間がかかっても進めていかなければならないと考えている。
(E委員) 収入が減る、ということだが、増やそうとする施策はないのか。
(事務局) ふるさと納税を含め、様々な施策を検討している。例えば市有地で利活用をしていないものを売却して民間に宅地造成してもらう、というようなことも考えられる。
質疑事項10.総括の全般について
(D委員) 全体的にはコンパクトにまとまっているが、それぞれの担当部署が、それぞれの取組みに対する反省点や改善点なども明らかにしてもらえると内容も把握しやすくなるのではないか。
(事務局) ご意見のとおり修正させていただきたい。
(E委員) 達成率の有効性については誰が評価することになるのか。
(事務局) 行革委員会や行革本部において評価することとなる。
質疑事項11.第5次行革推進計画「進行状況」「5広報広聴活動の充実」について
(D委員) 得点化されていないことは理解したが、分析は必要であると感じている。
(事務局) 評価項目が5段階のものが4段階に変更したことにより直接的な分析がでいなかった。客観的な指標の設定を考えたい。
その他
(A委員) PPPのデメリットは何か。
(事務局) 指定管理者制度でいえば、本来であれば施設管理に携わる職員の削減ができるはずができていないこと、指定管理者が雇う労働者の賃金が低下するおそれがるといういわゆる「ワーキングプア」の問題がある。指定管理は、受託者が収益を上げることができる仕組みが必要だが、いままでの運用ではそれがあやふやな面がある。ただ、道の駅のように指定管理料を出さずに独立採算で行っているところもあり、施設によってはメリット・デメリットの差がある面もある。
現委員の任期終了にあたり、各委員より挨拶あり。
5 閉会
ダウンロード
事前質疑に対する回答一覧 (PDFファイル: 92.3KB)
企画振興部 企画課
電話 :0123-33-3131(内線:2341)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
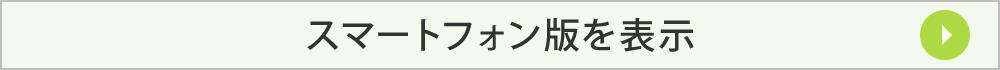








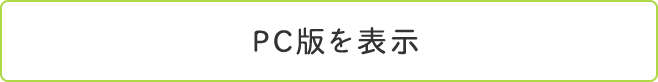

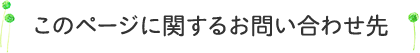
更新日:2019年03月29日