情報公開・個人情報保護審査会-令和元年10月30日
令和元年度第2回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会(担当課:総務部総務課)
1 開催日時
令和元年10月30日(水曜日)14時00分から15時00分まで
2 開催場所
市庁舎2階 204会議室
3 出席者
【委員】 亀石和代、白崎亜紀子、松本史典(50音順、敬称略)
*大岩則子委員及び森田祐一委員は、所用のため欠席
【市】(説明員)建設部都市整備課長、同主査、 保健福祉部障がい福祉課長、同主査
(事務局)総務部長、総務部次長、総務課長、法制担当主査、同スタッフ
【傍聴】 1名
4 審査会の経過
(注意)以下は、事務局が発言の要旨をメモにより要約しており、いわゆるテープおこしをしたものではありません。
〈1〉 会長挨拶
〈2〉 諮問
総務部長より、今回審査いただく事項1件について諮問しました。
〈3〉 報告
(1) 特定個人情報保護評価書について
(2) 前回の諮問・答申事項に係る補足説明について
〈4〉 議事(諮問事項)
柏陽団地建替事業の推進に係る家屋台帳情報及び上水道の契約情報の目的外利用について
*諮問内容について、建設部都市整備課長、同主査より資料をもとに説明
説明概要
恵庭市では、本年5月に策定した市営住宅柏陽・恵央団地建替基本計画に基づき、老朽化が進む市営住宅柏陽団地の建替えの検討と、それに伴う既存入居者移転を進めています。既存入居者の移転先としては、市内の市営住宅のほか、市内の民間賃貸住宅を有効に活用することを検討しています。
調査は、市内の民間賃貸住宅の総数や空き状況を把握することと併せて、それらを所有するオーナーに対してアンケート及びヒアリングを実施し、民間賃貸住宅を市営住宅として活用することに対する意向や課題等を把握するために行うものです。
実施主体について、調査は建設部都市整備課で行いますが、ヒアリング等については住宅課、まちづくり推進課と協同して行う予定です。調査の手段としては、家屋台帳より市内の民間賃貸住宅の戸数やオーナーの情報を把握し、上水道の契約状況より空き部屋の戸数等を把握したいと考えています。スケジュールについては年内にアンケートの発送、回収を行い、年明けにヒアリング調査の実施を予定し、年度内には調査の結果をまとめたいと考えています。
以上のことから、事務の効率的な執行のために、家屋台帳等の情報を所管課から目的外利用することを諮問します。
各委員からの質問・意見等の内容
委員
一戸建ては調査の対象となるか。また市営住宅の建替えが前提となっているが、例えば被災により避難してきた方等の受入れ先や移住の促進への活用を想定しているか。
説明員
一戸建ては対象としていません。また、現時点では既存入居者の移転のみを想定しており、それ以外の利用は想定していません。
委員
民間賃貸住宅によっては水道の契約をオーナーが一括で行っている場合もある。その場合は詳細な把握が困難と思うが、どのような対策を検討しているか。
説明員
現時点では個別の契約のみが調査の対象となります。ご指摘の対策については今後検討していきます。
委員
ここで言う柏陽団地とはJR沿線に位置する団地群のどちらも指しているか。またそうだとすれば世帯はどの程度か。
説明員
柏陽団地についてはそのとおりです。対象となるのは238世帯と把握しています。
委員
今後調査を経て、民間賃貸住宅を市営住宅として活用する場合、
(1) 民間賃貸住宅から新設する団地に戻ることはできるか。
(2) 民間賃貸住宅の入居者間で家賃の不均衡が起こると思うが、どのような対策を検討しているか。
(3) 他自治体の事例はあるか。
説明員
(1) そのような事態は想定していません。現入居者へ意向調査を行った結果を踏まえて、現入居者の受入れ先を検討していきたいと考えています。
(2) 市は入居者から公営住宅法に基づいて算定された使用料を徴収し、民間賃貸住宅のオーナーに対しては契約した家賃をお支払いすることになります。入居者から徴収した使用料と契約家賃の差額分は、市と国の補助金で負担することとなります。
ご指摘の入居者間の家賃の不均衡は想定されます。現在も部屋によって家賃が異なる場合はあり得ますが、例えば一棟を借り上げる等、家賃の不均衡が極力発生しない仕組みは必要と考えています。
(3) 千歳市や小樽市が一棟を借り上げる形で実施しています。空き部屋だけを借り上げる事例は道内では見られません。
委員
新設する団地の戸数はどの程度か。また現在の市営住宅はどの程度空いているか。
説明員
新設する団地は140戸を計画しています。現在の入居状況について詳細な把握はしていませんが、所管課より一定数あると聞いています。
委員
アンケート調査の実施後にオーナーとヒアリングを行った結果、民間賃貸住宅の借上げを行わないという判断もあり得るか。
説明員
そのような判断も含めて、現状を把握するものです。
*説明の聞き取りが終わり、説明員及び傍聴者退席
答申内容
柏陽団地建替事業の推進に係る家屋台帳情報及び上水道の契約情報の目的外利用をすることは妥当である。
ただし、附帯意見については、事務局と協議のうえ付することとする。
*協議が終わり、傍聴者再度入室
〈5〉 その他
(1) 特定個人情報保護評価書について(総務部総務課より説明)
マイナンバーが付与される個人情報を取り扱う前に個人のプライバシーに与える影響を予測し、評価するために行われる「特定個人情報保護評価」について、前回の審査会以降、基礎項目評価を行った事務で本審査会において報告していなかったものが1件ありましたので報告いたします。
該当する事務は「寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務」となっております。担当部署は企画課、公表日が令和元年10月17日となっております。詳細は資料をお読み取りください。
なお、何度か説明しているところですが、過去1年以内に特定個人情報に関する重大事故を発生させた場合、基礎項目評価をさらに詳しくし、リスク対策等についても記載する「重点項目評価」を行うこととなります。この場合は、本審査会において評価を行っていただくようお願いすることとしておりますので、よろしくお願いいたします。
今後も、基礎項目評価書を作成した事務については、本審査会にてご報告させていただきます。
(2) 前回の諮問・答申事項に係る補足説明について(保健福祉部障がい福祉課より説明)
趣旨
「日常生活用具給付等事業、地域生活支援給付事業及び社会参加促進事業の申請に係る所得情報及び課税情報の目的外利用について」は、前回の審議会において諮問し、承認いただいたところであるが、委員より再度説明を求める旨の提案があったため、それを受けて担当課より諮問の趣旨等について再度説明を行うもの。
各委員からの質問・意見等の内容
委員
前回の確認ということだが、家族の判断はどのように整理するか。
説明員
障がいサービスが必要という家族を含めた本人の意思を確認するためにこれまで自署や押印がなされてきましたが、障がいの特性もあり押印漏れ等の不十分な申請書が提出されることが実態です。サービスが必要という意思を書類の提出によって確認し、支給決定の事務を行うという趣旨です。
委員
資料13ページに記載の地域生活支援事業で自署や押印が必要なものはどれか。
説明員
記載の事業は全て必要です。同じ障害者自立支援法に規定されている事業であっても、障がい福祉サービスと地域生活支援事業で押印や自署を必要とするものとしないものに分かれており、利用者が混乱する一因となっています。地域生活支援事業は市町村の実情に合わせて実施することができますが、障がい福祉サービスと調査の権限が異なっているため、いわゆる法令の「横出し」としての上位法と同じように事務を行いたいと考えています。
委員
申請は毎年しなければならないのか。
説明員
そのとおりです。事業によっては3か月毎に申請が必要なものもあります。
委員
既に申請を行っている方以外に、新規に申請する人にも負担がないようにという趣旨も含んでいるか。
説明員
そのとおりです。自署による申請行為をもって手続を行いたいということです。
*説明の聞き取りが終わり、説明員及び傍聴者退席
委員による承認の確認
〈6〉 閉会
15時00分終了
ダウンロード
関連リンク
総務部 総務課
電話 :0123-33-3131(内線:2211・2212)
ファックス :0123-33-3137
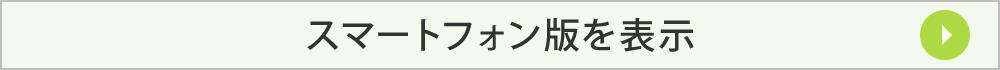








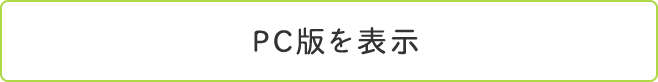

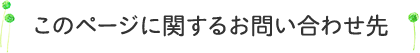
更新日:2019年11月29日