情報公開・個人情報保護審査会-平成30年2月7日
平成29年度第1回情報公開・個人情報保護審査会 (担当課:総務部総務課)
1 開催日時
平成30年2月7日(水曜日)13時30分から14時15分まで
2 開催場所
市庁舎2階 202会議室
3 出席者
【委員】大岩則子、亀石和代、白崎亜紀子、松本史典、森田祐一(50音順、敬称略)
【市】(説明員)保健福祉部福祉課長、同主査 子ども未来部子ども家庭課主幹、同主査 保健福祉部国保医療課長、同主査
(事務局)総務部長、総務部次長、総務課長、法制担当主査、同スタッフ
【傍聴】なし
4 審査会の経過
(注意)以下は、事務局が発言の要旨をメモにより要約しており、いわゆるテープおこしをしたものではありません。
<1>会長挨拶
<2>諮問
総務部長より、今回審査いただく事項2件について諮問しました。
<3>議事(諮問事項)
(1)法令に基づく調査権限を有する課に対する生活保護受給の開始、停止及び廃止の情報の提供について
(注意)諮問内容について、保健福祉部福祉課長、同主査より資料をもとに説明
(説明概要)
生活保護の開始にあっては、課税の法定免除や国民健康保険の資格喪失の手続を、生活保護の停止及び廃止にあっては、課税や国民健康保険の資格取得等の手続を遅滞なく行わなければなりません(不要な賦課徴収や保険給付等が続いてしまうことや、逆に免除・減免されるべき税負担等が免除・減免されないため)。
通常、保護の開始や停廃止時には、保護受給者に対し担当ケースワーカーがこれらの手続について案内を行います。しかし、別紙2にも記載のとおり、保護開始時に本人の申請意思を確認できないが、急迫状態にあるような職権による保護開始や、保護受給者の失踪等により保護が停廃止等する場合もあり、通常ケースのように開始・停廃止時に手続が速やかに行えないことがあります。
現在、法令等の調査権限に基づく目的外利用(恵庭市個人情報保護条例第9条第1項第1号)により、別紙4のとおり各課からの調査依頼があり、それに対し生活保護受給の有無について回答を行っていますが、調査対象者が膨大であり、回答までには多くの時間と労力を要しております。
以上から、相互の事務負担の軽減を図るため、今後、福祉課にて毎月、生活保護受給者の異動者情報を抽出し、法令に基づく調査権限を有する課へ情報提供を行うことについて諮問するものであります。
各委員からの質問・意見等の内容
委員
調査に対する回答作業はどのように行われているのか。
説明員
調査対象者のデータを提出いただき、福祉課でパソコンを用いて突合作業を行います。生活保護受給者は必ずしも住民票上の住所に居住しているわけではなく、例えば施設に入所している場合は施設の住所を届け出ている場合があります。その場合、パソコンだけでは突合できず、手作業で行う必要があるため、時間と労力がかかってしまいます。
委員
調査件数はどの程度あり頻度はどのくらいか。
説明員
おおむね別紙4に記載のとおりとなります。頻度については、定期的又は必要に応じて随時調査依頼があります。
総務部長
調査件数は膨大な数になります。生活保護の受給も日々異動があり、各部署においても生活保護受給者の異動情報を把握しなければならない事業も多くあります。
委員
本件が承認されたらどのように事務が変わるのか。
説明員
月15件くらいの生活保護受給者の異動情報を提供先の各課で突合してもらうことになります。
委員
調査の対象としない者の情報も提供することになるとはどういうことか。
説明員
生活保護受給者は幅広く受給されています。一例としては、子を持つ若年の母親の生活保護受給情報が事務の対象になり得ない介護福祉課に情報が入ってしまう等のことが考えられます。
委員
恵庭市の生活保護受給者はここ数年増えているのか。
説明員
若干の減少傾向にあります。1月末現在で1,000人当たり13.9人となっております。本市で1番多い時で1,000人当たり16.0人であったと記憶しております。
委員
申請自体が減っているのか。生活保護申請に対する受給の開始が減っているのか。
説明員
受給者の数より廃止となる者の数が上回っていると記憶しております。
総務部長
生活保護受給者に対する就労相談等の自立できるような体制の整備により受給者数や保護費も減少傾向にあります。制度的にも様々な周辺環境整備の充実もあり、数字に大きな影響を与えているものを思われます。
委員
調査の対象としない者の情報も提供することになるが、提供先への対処はあるか。
説明員
提供先には一般の職員よりも重い守秘義務が課せられること、そして回覧をする際の取扱いについて十分に注意することを徹底したいと考えております。
委員
ケースワーカーは、個々の生活保護受給者のもとに訪問したり現況報告等を求めたりするのか。
説明員
ケースワーカーはそれぞれ担当する世帯を持っています。世帯ごとに年間何回の訪問をするかを決め、随時家庭訪問行います。生活状況を確認したり、就労している者又は求職活動をしている者に対しては就労状況や求職状況を確認したりするなどし、それらをもとに保護の決定を行っている状況です。
委員
マスコミ等で一度に多くの個人情報が流出したとのニュースを見ると恵庭市でもありえない話ではないと思っている。個人情報の厳重な取扱いが今まで以上に必要かと思われる。関係のない部署への情報提供について守秘義務があるとはいえ心配な部分もある。
総務部長
新聞やニュース等において、個人情報の取扱いの問題で事件につながったとの指摘も多くあります。本市においても取扱いについての周知を定期的に行っており、今後も取扱いについては厳重にするよう徹底していきたいと思います。
委員
提供する6つの課には、回覧する者を1人に限定する等の縛りはあるのか。
説明員
業務を複数で行っていることが多く、1人に限定することは難しいが、業務を担当する職員のみに回覧を制限するので、一定の縛りがあるものと考えております。
(注意)
説明の聞き取りが終わり、説明員退席
答申内容
法令に基づく調査権限を有する課に対する生活保護受給の開始、停止及び廃止の情報の提供をすることは妥当である。
ただし、附帯意見については、事務局と協議のうえ付することとする。
(2)ひとり親家庭支援事務(児童扶養手当・ひとり親医療費助成)利用者情報の目的外利用について
(注意)諮問内容について、子ども未来部子ども家庭課主幹、同主査、保健福祉部国保医療課長、同主査より資料をもとに説明
(説明概要)
子ども家庭課の事業の「児童扶養手当業務」と、国保医療課の事業の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者はどちらもひとり親家庭となっております。
どちらの業務も適正な受給の確保には、受給者の資格の把握に努め、支給要件を欠く場合は、本人との面談による聞き取り等を実施するなど確認が必要ですが、戸籍や住所に変動のない世帯構成等の変化については、その現状を把握することは困難です。
特に、受給者が婚姻の届出がなされていない事実婚(頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合)状態である場合には、両事業とも受給要件から外れ、手当や助成が停止となりますが、本人からの積極的な申請を得ることは難しい状況となっております。
一例ですが、児童扶養手当業務の場合、受給者宅への異性の出入りや金銭的に羽振りが良い場合などに近隣住民等からの受給にかかる疑義について通報があることがあります。その場合は、児童扶養手当法第29条の調査権により調査を実施し、受給資格の有無や手当額の決定のための養育費に係る額等を調査することになります。
調査の結果、事実婚をしている場合や、本人の養育費の申告漏れにより所得に変動がある場合は、児童扶養手当が停止や減額になる場合があります。
原則、児童扶養手当を廃止する場合は、受給者から「喪失届」の提出を求めますが、本人が応じない場合等は職権により廃止する場合もあります。
そのような状況の場合は、本人から同意を得ることも、ひとり親家庭医療費助成事業窓口での廃止手続を促すことも困難です。
児童扶養手当受給資格喪失後に受けたひとり親家庭等医療費の助成額は返還することになります。個人差はありますが、受診の内容によっては高額となる場合もあります。
よって、受給資格を相互に確認し合うことは、受給者の捕捉の有効な手段になると考えます。
情報を共有する主な内容は、(1)受給者氏名、(2)受給者の住所、(3)資格履歴、(4)現況情報です。
現況情報の内訳は、子ども家庭課においては、福祉世帯情報、支払履歴、所得情報、所得判定詳細情報、停止情報、国保医療課においては、福祉世帯情報、保険情報、給付確認、所得判定詳細情報、対象児童情報となっております。
この情報は、現在、子ども家庭課、国保医療課で使用している保健福祉総合システムにより共有することが可能となっております。
以上のことから、両事業とも、ひとり親家庭への福祉制度であり受給要件が重複するところが多い事業でありますので、市にとっては適正な支給の確保のため、また、受給者にとっては返還金が生じることによる不利益の解消のために、相互に情報を連携し、受給資格を把握し合うことは、公共の利益及び本人の利益になると考えるため恵庭市個人情報保護条例第9条第1項第4号に規定する目的外利用による情報の提供について本審査会に意見を求めるものです。
各委員からの質問・意見等の内容
委員
両事業で1年に1回行っている本人からの現況報告を確認するということか。
説明員
年1回の現況報告において家庭状況等について確認を行うが、年度の途中で状況が変わった場合を速やかに把握するために、目的外利用が必要であり諮問するものであります。
委員
1年経過しないと状況の変化が把握できないため、その都度、情報が必要ということか。
説明員
そのとおりです。
委員
両事業で過去に齟齬があったのか。
説明員
最近そのような事案があり、支給できる者に支給がされていなかったり、その逆もありました。
委員
市民は支給されるという知識や情報がなかったことによるものか。
説明員
児童扶養手当については、離婚した際に説明を行っています。離婚した場合、所得がある方は児童扶養手当の受給要件から外れてしまいます。また、現況届は現に受給している方に案内を送付しているため、1度児童扶養手当の受給要件から外れてしまうと案内が送付されないことなります。ただし、その方に医療費がかかったときに病院の照会によりひとり親医療助成を受けていたが、その情報が児童扶養手当の担当に情報が来ていなかったことにより児童扶養手当が受給していなかったというケースがありました。
委員
情報共有をすることによりそのようなことは今後なくなるのか。
説明員
どちらも受けられない方が出てくることもあるが、どちらかの助成を受けていればその情報を元に他方の助成も受けることができることになります。
委員
申請を適正に行わない方も把握することができることになるのか。
説明員
例えば事実婚が判明し児童扶養手当の支給が廃止になれば、その情報を元にひとり親医療助成の受給も廃止することができることになります。
(注意)説明の聞き取りが終わり、説明員退席
答申内容
ひとり親家庭支援事務(児童扶養手当・ひとり親医療費助成)利用者情報の目的外利用をすることは妥当である。
ただし、附帯意見については、事務局と協議のうえ付することとする。
会長
本日2件の諮問事項について、担当職員にあっては個人情報の取扱いを厳正に行うよう徹底し、事故等につながらないよう附帯意見として盛り込みたいと思います。
<4>その他
- 過去に答申した「恵庭市災害時要援護者支援のための個人情報の目的外利用及び外部提供について」の進捗状況について
会長
自主防災組織の結成のために早急に情報が必要とのことから、その必要性を審査し答申したが、その後、自主防災組織が数団体しか結成されていないと聞いている。現在の進捗状況について説明願います。
総務部次長
本件につきましては、平成20年に諮問し答申をいただいた案件でありますが、平成26年に法改正があり、市町村に災害発生時に支援を要する避難行動要支援者の名簿作成が義務付けられました。結果、条例の適用外になりましたが、市でも名簿を作成し該当者2,000名ほどに対して平時から情報を取り扱うため、本人同意をもらう事務を進め、現在500名ほどの同意をいただいたところであります。新たに転入された方などで障がいのある方や介護が必要な方にあっては、申請時に個々に案内しております。
自主防災組織の組織数は、現在34団体であり、覚書を交わして名簿の提供をした団体数は30団体に上ります。2年に1回は同意いただいた方全員に確認を行い、同意をいただくこととしております。名簿は1年に1回更新を行いますが、その際に提供した名簿を回収し、新しい名簿の交付を行います。名簿のコピーは極力行わないようしていますが、必要な場合にあっては台帳を整備し、コピーも全て回収を行うこととしております。
会長
昨年、自主防災組織の結成していない町内会に対し説明会を行ったと聞いているが、今後も行っていくのか。
総務部長
現在、62町内会のうち34団体で結成され、約半分近くになるが、世帯数となると市内約3万3,000世帯うち約2万4,000世帯が自主防災組織の対象世帯であり、その割合は73.1パーセントに上ります。北海道では約56パーセントであり、全国的には約82パーセントであることから、全国レベルには及びませんが道内レベルを上回っている状況にあります。
近年の台風等の影響もあり、ここ2年間で10組織が増えております。現在、4つの町内会が自主防災組織の結成に向けて前向きに検討いただいております。この4町内会を含めると80パーセントを超えるものと試算しております。
これからも災害に強い地域防災を構築していきたいと思っております。
<5>閉会
14時15分終了
ダウンロード
関連情報
関連リンク
総務部 総務課
電話 :0123-33-3131(内線:2211・2212)
ファックス :0123-33-3137
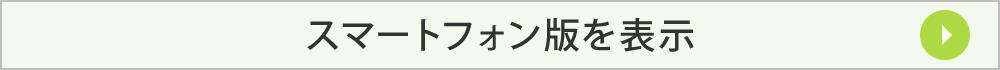








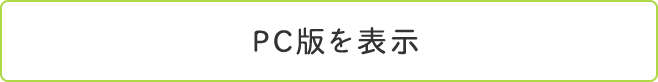

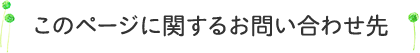
更新日:2019年03月29日