情報公開・個人情報保護審査会-平成27年1月30日
平成26年度第2回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会
(担当課:総務部総務課)
1 開催日時
平成27年1月30日(金曜日)13時30分から14時20分まで
2 開催場所
市庁舎3階 301・302会議室(傍聴者:なし)
3 出席者
【委員】亀石和代、川口れい子、松本史典、村本満子、森田祐一(順不同、敬称略)
【市】(説明員) 生活環境部次長、生活安全課長
(事務局)総務部長、総務部次長、総務課長、法制・文書担当主査、同スタッフ
4 審査会の経過
(注意)以下は、事務局が発言の要旨をメモにより要約しており、いわゆるテープおこしをしたものではありません。
(1)会長挨拶
(2)諮問
総務部長より、今回審査いただく事項について諮問しました。
(3)報告事項
恵庭市暴力団排除条例の制定に係る個人情報の取扱いについて
(注意)報告内容について生活環境部生活安全課長より説明
恵庭市では、暴力団の排除に関し基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び地域経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、「恵庭市暴力団排除条例」を制定し、平成27年4月1日から施行します。
条例第14条において、「この条例に基づき暴力団の排除を図ることを目的として、必要かつ最小限の範囲内で個人情報を収集すること及び警察その他の関係機関に提供し、当該個人情報に係る個人が暴力団員であるかどうかの確認をすることができる」とされたことから、その旨をご報告します。
(4)諮問事項
空家の実態調査に係る個人情報の目的外利用について
(注意)諮問内容について生活環境部次長より説明
恵庭市においては、「空地の環境保全に関する条例」は制定されていますが、「空家」に関しての条例は制定しておりません。
また、空家に関係する担当の部署について、危険な空家に対する生活環境の保全に関しては生活安全課、空家の住み替え等の有効利用についてはまちづくり推進課と、部署が分かれておりました。そうしたことから、庁内の検討会議を立ち上げる等の対応を行ってきたところです。
この度、国では「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定され、市町村の計画の策定や空家等の所有者等に関する情報の内部利用について規定されました。法は平成26年11月27日に公布されており、公布の日から起算して3ヶ月以内で政令で定める日から施行するとされています。
そのため、内部で利用する個人情報の利用範囲等を明確にするため及び法の施行の前においても事務を進めるため、個人情報保護条例第9条第1項第4号に規定する目的外利用について、本審査会に意見を求めるものであります。
3 各委員からの質問・意見等の内容
委員
市内にどのくらいの空家があるのですか?
説明員
倒壊しそうな空家はないと把握している。
委員
空家になって何年か経つと更地にしなければならないというのは決まっていないのですか?
説明員
決まっていない。建物が建っていると税の軽減措置が受けられるというのが空家が残る原因にもなっていると考えている。
委員
市民から迷惑な建物があるという通報はないですか?
説明員
空家の関係では年数件の連絡がある。「隣の家にある木の枝が入る」「雪で倒壊しそう」という内容のもの。連絡があれば対処し、継続中の問題はない。台風の時期には屋根が飛びそうという連絡があり、市消防本部と連携して対応したという事例もある。
委員
対応した案件で持ち主が分からないというのはないですか?
説明員
これまではない。
委員
空家の定義はどのようなものですか?
説明員
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条において「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう」とされている。
委員
空家かどうかを調査するために調べるのですよね?
説明員
そうです。水道部経営管理課において所有している水道メーターの検針状況を確認し、そこで1年以上未使用である場合は、総務部税務課で所有している税情報とあわせて、対象物件を把握したいと考えている。
委員
他市はどのような取組みをしているのですか?
説明員
道内他市でも同様の取組みをしている自治体はあるが、石狩管内ではあまり取り組んでいる自治体はないようです。その地域によって対応は異なると考えている。
委員
空家等対策の推進に関する特別措置法が制定されたことにより対応することとなったのですか?
説明員
社会問題にもなっていることから、法が制定される前から検討していた。
委員
空家の実態を把握したあとは、どのような対応をするのですか?
説明員
空家の危険度の基準を作り、その中で危険度に応じた対応をしたい。また、法では協議会の設置も規定されているので、そういった検討もしていきたい。最終的には所有者との協議となるが、地域住民が安心して暮らせるように対応をしていきたい。
(注意)説明の聞き取りが終わり、説明員退席
意見
地域住民の安心・安全につながるものであり、個人情報の目的外利用は妥当だと考える。
意見
事務の効率化の面でも妥当だと考える。
5 答申内容
空家の実態調査の実施のため、関係する個人情報を目的外利用することは妥当である。
ただし、以下の附帯意見を附する。
- 市は、利用する個人情報の取扱いや管理には厳重に注意するとともに、本事業に係る事務を行う以外の目的に利用しないよう徹底すること。
- 市は、個人情報の目的外利用にあたっては、対象者ごとに必要な個人情報を確認のうえ、対象者以外の情報及び提供範囲を超える情報などが含まれないよう厳重に注意するとともに、関係事務の担当者に限り取り扱うよう徹底すること。
6 その他
(1)今後の審査会の所掌事務について(総務部総務課より説明)
本審査会の委員の任期が平成27年6月30日までであることから、次期の任期にあわせ所掌事務を拡大したく、今回の審査会においてご説明させていただくものです。
大きくは2点、本審査会の所掌事務を拡大します。
1点目は、番号法(国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や納税に関する情報を一元的に管理する「共通番号(マイナンバー)制度」)が全国的に始まりますが、その施行に伴う事務です。資料にはありませんが、こちらは本年7月の委嘱の段階から追加する役割と考えております。
2点目は、行政不服審査法の改正に伴う、市の機関が裁決を行う前に第三者機関から意見を聴くために設けられる機関としての役割です。こちらは、平成28年4月1日から追加する役割と考えております。
まず、1点目の番号法の施行に伴う事務です。行政では、マイナンバーが付与される個人情報を取り扱う前に個人のプライバシーに与える影響を予測・評価するために行う「特定個人情報保護評価」というものを行います。
その評価を行うにあたり、それぞれの事務ごとに“しきい値”判断というものを行います。しきい値判断は事務ごとに対象人数やその事務を担当する職員の人数等に基づいて判断を行います。
恵庭市はすべての事務において“基礎項目評価”という一番簡素な評価となります。しかし、「過去1年以内に特定個人情報に関する重大事故を発生させた」場合は、“重点項目評価”という評価を行うこととなります。
法律上は、“重点項目評価”で第三者機関の点検を義務付けてはいませんが、恵庭市としてはこの“重点項目評価”になるのが重大事故を発生させた場合のみであるため、その点を鑑み“重点項目評価”における第三者機関の点検を行うこととし、それを本審査会にお願いしたいというものであります。
役割についてですが、評価書は行政が作成し決定しますが、その評価の適合性・妥当性を本審査会に担っていただくこととなります。
次に、行政不服審査法の改正に伴う事務についてです。
平成28年4月1日施行予定で行政不服審査法が改正され、行政処分を受けた者が市の機関に対して審査を申し出た場合において審理員(市の職員)を設置し、その者が請求者及び市の機関の意見を聴取し意見書を作成し、その意見書をもとに市の機関が裁決を行うこととなります。この場合において、市の機関が裁決をする前に、有識者からなる第三者機関の意見を聴かなければならないこととなったことから、この第三者機関の役割を本審査会にお願いしたいというものであります。
役割としては、はじめから審理するのではなく、第三者の視点で審理員による事実認定を検分した上で、法令解釈等の妥当性を検証する役割を担っていただくというものであります。
以上の役割となりますが、なぜ本審査会にお願いすることとなったかといいますと、1点目の番号法の施行に伴う事務については個人情報の保護がしっかり行われるかという観点から評価書を確認していただく必要があり、個人情報保護審査会としての役割を担っていだいている本審査会の役割と共通する部分があると考えたからです。
また、2点目の行政不服審査法の改正に伴う事務についてですが、本審査会の現在の役割として、「公文書公開請求のあった文書の公開・非公開の決定に請求者が不服の場合は審査を行う」というものがあり、不服に対して審査を行うという観点が共通している点や、行政の判断の妥当性をチェックする役割であることから法令解釈等の知識も必要であり「弁護士、行政書士等」の方にお願いしたいという点から、本審査会に求められる人材と共通すると考えたからです。
以上簡単ですが、このような理由から今後の本審査会の事務分掌を拡大させて頂きたいと考えております。よろしくお願い致します。
(2)前回の諮問・答申事項に係る運用状況の報告(総務部総務課より報告)
前回の審査会で答申を受けました事項に係る、答申後の運用状況について報告いたします。
まず、「臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金事業実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について」の答申後の運用状況ですが、答申いただいた際の附帯意見として附された事項(・個人情報の取扱いや管理には厳重に注意するとともに、本事業に係る事務を行う以外の目的に利用及び提供しないよう徹底すること。・対象者以外の情報及び提供範囲を超える情報などが含まれないよう厳重に注意するとともに、関係事務の担当者に限り取り扱うものとし、個別の案件に応じて関係課を限定して利用するよう徹底すること。)を徹底したうえで、目的外利用及び外部提供したことを報告いたします。
また、2件目の「農地台帳の整備に係る固定資産税情報の目的外利用について」ですが、答申いただいた際の附帯意見として附された事項(・固定資産税情報の取扱いや管理には厳重に注意するとともに、農地台帳の整備に係る事務を行う以外の目的に利用しないよう徹底すること。・対象地番以外の情報及び提供範囲を超える情報などが含まれないよう厳重に注意するとともに、関係事務の担当者に限り取り扱うよう徹底すること。)を徹底したうえで、目的外利用しております。
3件目の「死亡者に関する個人情報の取扱いについて」につきましては、答申後、審査会の答申を全庁に周知したところですが、死者に関する情報の開示請求は、今のところありません。
終了14時20分
ダウンロード
関連情報
総務部 総務課
電話 :0123-33-3131(内線:2211・2212)
ファックス :0123-33-3137
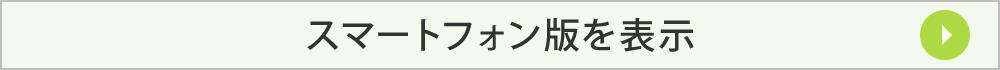








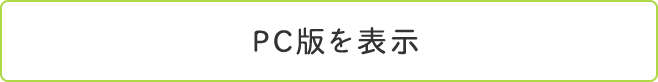

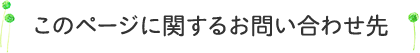
更新日:2019年03月29日