情報公開・個人情報保護審査会-令和元年7月23日
令和元年度第1回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会(担当課:総務部総務課)
1 開催日時
令和元年7月23日(火曜日)13時30分から14時15分まで
2 開催場所
市庁舎2階 204会議室
3 出席者
【委員】大岩則子、 亀石和代、白崎亜紀子、松本史典、森田祐一(50音順、敬称略)
【市】(説明員) 保健福祉部障がい福祉課長、同主査、同スタッフ
(事務局)副市長、総務部長、総務部次長、総務課長、法制担当主査、同スタッフ
4 審査会の経過
(注意)以下は、事務局が発言の要旨をメモにより要約しており、いわゆるテープおこしをしたものではありません。
〈1〉 委嘱状の交付
〈2〉 副市長挨拶
〈3〉 自己紹介
〈4〉 会長及び副会長の選出
委員の互選(事務局案)により、会長に亀石氏、副会長に松本氏を選任
〈5〉 会長・副会長挨拶
〈6〉 諮問
総務部長より、今回審査いただく事項1件について諮問しました。
〈7〉 報告
(1) 平成30年度公文書公開状況及び個人情報開示状況について
(2) えにわプレミアム付商品券事業について
「えにわプレミアム付商品券事業」が実施されるに当たり、過去の答申にある「今回と同様又は類似する趣旨及び内容の事業に限り、この答申内容に準じた取扱いのもと、個人情報を目的外利用及び外部提供することができる」という附帯意見に基づき、類似する事業と判断して個人情報の目的外利用及び外部提供を行う旨を報告した。
〈8〉 議事(諮問事項)
日常生活用具給付等事業、地域生活支援給付事業及び社会参加促進事業の申請に係る所得情報及び課税情報の目的外利用について
*諮問内容について、保健福祉部障がい福祉課長、同主査、同スタッフより資料をもとに説明
説明概要
障害者総合支援法によるサービスは、自立支援給付の障害福祉サービス、自立支援医療及び及び補装具と地域生活支援事業に分かれており、地域生活支援事業は地域の実情に応じて実施できる市町村事業となっております。今回の日常生活用具給付等事業、地域生活支援給付事業である移動支援事業、福祉ホーム支援事業、訪問入浴サービス支援事業、日中一時支援事業の4事業と、社会参加促進事業である身体障害者自動車改造支援と身体障害者自動車運転免許取得支援の2事業は、市町村事業の地域生活支援事業となっております。
自立支援給付の障害福祉サービスについては、障害者総合支援法第12条に課税状況などを把握する際に、市町村が自ら調査を行うことを可能とする規定を設けております。一方で、今回の市町村事業である地域生活支援事業は、市町村の要綱に基づいて実施するもので、事業を利用する際は、申請時に、所得調査などに同意していただき、同意欄に氏名、住所を記入し、押印をいただいています。
書類の記入については、障がいがあったり、高齢であったりするなど、不自由な方が多く、負担感があります。利用者から見ますと、障害福祉サービスと地域生活支援事業の区別がわかりづらく、同意欄の有無によって、手続の際に印鑑を忘れたために再来庁を求めるなどの事象が起こっております。
なお、平成30年度の利用者については日常生活用具給付事業182名、地域生活支援給付事業69名、社会参加促進事業3名で、合計254名となっております。
以上のことから、障がいのある方の負担軽減のために、同意書を求めずに課税情報を所管課から目的外利用することを諮問します。
各委員からの質問・意見等の内容
委員
障がいのある方については、一律に同意を取らずに、課税情報を目的外利用するということになるのか。
説明員
同意を得ることを原則としつつ、印鑑を忘れたときや自力で文字を書くのが困難な場合、代理の者が書類を提出する場合などは、再来庁を求めずに対応することとしたいと考えております。また、実際の所得調査では、障がい者本人だけではなく世帯全員の課税状況等にも基づき給付の審査を行う必要がありますが、現状では障がい者本人に家族の分についても調査して良いかどうか、同意をもらっているという状況になっております。同じ障害者自立支援法に規定されている事業であっても、障がい福祉サービスと地域生活支援事業とで、給付する際の調査の権限が異なっておりますが、それを同一の基準で調査し、給付の審査を行いたいと考えております。
委員
諮問による目的外利用する場合とそうでない場合(本人同意による場合)の基準はあるのか。
説明員
申請書の下段にある同意欄に記名押印していただくことを原則としますが、仮になくても同意があるものとみなして取り扱いたいということです。
委員
一定の要件に該当する障がい者であれば、(同意を取らなくても)市が調査をすることが多いという印象だが、そうではないのか。
説明員
法令において市が調査をすることができる旨の規定があるものについては可能ですが、地域生活支援事業は市の要綱で定めているものですので、今回諮問しております。
委員
これまでの説明を受けると、同意欄に記名押印しなくても課税情報を得ることができる、としたいのか。
説明員
現在は、同意欄に不備がある場合は給付の審査ができないため、課税状況がわかるものや印鑑を持って再度来庁していただくようにお願いしている状況です。同意欄に不備がなくなったうえで課税情報を取得しております。
委員
今のやり方では事務が進まないという状況にあるのか。
説明員
そうではなく、再来庁などの障がい者の負担感の軽減を図りたいと考えております。市としては、書類に不備があったり、課税状況が把握できなければ、支給できないという結果にしかなりません。
委員
障がい者の代理の方が申請に来る場合は、委任状などを持ってくるのか。
説明員
委任状は特になく、申請者欄が障がい者本人であれば受付をしております。代理人はあくまで書類を持ってきただけということです。
委員
申請時のやりとりは1回で終わらないことのほうが多いのか。
説明員
数としては少ないですが、郵送による申請や本人以外の申請となると不備があった場合には何度かやりとりをすることになってしまいます。
委員
確認だが、最初の説明の中で述べられた数字は、昨年度の実績か。
説明員
そのとおりです。ちなみに、日常生活用具給付において大半を占めるのは、蓄便袋や蓄尿袋に係る申請であり、昨年度の182名のうち約9割がこれに当たります。
委員
申請数は増えている傾向にあるのか。
説明員
微増ですが、増えている傾向にあります。地域生活支援給付事業は、継続的に利用される方が大半ですので、これに新規の方が加わるような状況です。
委員
申請は毎年しなければならないのか。
説明員
そのとおりです。毎年の申請時に、その年の課税状況を確認し、それに応じて支給を決定することになります。
委員
法令の「横出し」の部分を補完する意味合いか。
説明員
そのとおりです。
委員
諮問書の「諮問内容」にある「所得調査等」の「等」とは何を指しているのか。
説明員
世帯全員の住民基本台帳の情報と所得の情報です。事業によって、課税情報が必要な場合と収入状況が必要な場合があるので、それぞれ取得する情報を使い分けております。
委員
確認だが、諮問の意図としては、障がい者の負担軽減ということか。ともすると、職員の負担軽減のため(手数を少なくするため)に目的外利用をしようとしているように見えなくはない。
説明員
障がい者の負担軽減のためです。
*説明の聞き取りが終わり、説明員退席
答申内容
日常生活用具給付等事業、地域生活支援給付事業及び社会参加促進事業の申請に係る所得情報及び課税情報の目的外利用をすることは妥当である。
ただし、附帯意見については、事務局と協議のうえ付することとする。
会長
目的外利用をする際には、個人情報の取扱いを厳正かつ慎重に行うようにすることを附帯意見として盛り込みたいと思います。
〈9〉 その他
(1) 特定個人情報保護評価書の様式の変更について(総務部総務課より説明)
マイナンバーが付与される個人情報を取り扱う前に個人のプライバシーに与える影響を予測し、評価するために行われる「特定個人情報保護評価」について、前回の審査会以降、様式に変更がありましたので、報告いたします。
今回の様式の変更は、特定個人情報保護評価に関する規則の一部を改正する個人情報保護委員会規則及び特定個人情報保護評価指針の一部を変更する件が、平成31年1月1日より施行されたことに伴う変更であります。
1点目は、「評価実施機関における担当部署」の「所属長」欄を「所属長の役職名」に変更したことです。
従前の基礎項目評価書の様式においては、評価を実施する担当部署の所属長の氏名の記載を求めていたため、人事異動の度に評価書を修正しなければならなかったところですが、事務負担の軽減の観点から、所属長の氏名の記載が省略されました。
2点目は、基礎項目評価書の記載事項として、リスク対策の実施状況を新たに加えるため、様式「4. リスク対策」の項目が追加されたことです。
これは、小規模な地方公共団体等であっても、リスク及びその対策の認識を深めてもらう観点から、最低限のリスク対策に関する措置状況等を確認するための記載欄を、基礎項目評価書の様式に設けるものであります。
以上のように国の個人情報保護委員会において議論された結果、様式が変更となっております。
なお、何度か説明しているところですが、過去1年以内に特定個人情報に関する重大事故を発生させた場合、基礎項目評価をさらに詳しくし、リスク対策等についても記載する「重点項目評価」を行うこととなります。この場合は、本審査会において評価を行っていただくようお願いすることとしておりますので、よろしくお願いいたします。
今後も、基礎項目評価書を作成した事務については、本審査会にてご報告させていただきます。
(2) 前回の諮問・答申事項に係る運用状況の報告について(総務部総務課より説明)
昨年10月22日に開催された平成30年度第1回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会において、3件の諮問・答申がありました。
はじめに、「重度障がい者タクシー料金助成事業に係る課税情報の目的外利用について」の答申後の運用状況についてでありますが、3つの附帯意見を徹底したうえで、2月の送付時に課税情報を確認し、業務を実施しております。
件数につきましては、手帳保持者(身体障害者手帳の等級が1級及び2級である者、療育手帳の判定がA判定である者、精神障害者保健福祉手帳の等級が1級である者)1,310名のうち、課税情報を利用して920名に送付しました。なお、申請者は、7月11日現在で517名と報告を受けております。
次に、「人工透析患者通院交通費助成事業に係る課税情報の目的外利用について」の答申後の運用状況についてでありますが、3つの附帯意見を徹底したうえで、2月の送付時に課税情報を確認し、業務を実施しております。
件数につきましては、腎臓機能障がいにより身体障害者手帳を保持している者151名のうち、課税情報を利用して94名に送付しました。なお、申請者は、7月11日現在で68名と報告を受けております。
最後に、「高齢者等のインフルエンザ予防接種及び肺炎球菌ワクチン予防接種に係る接種対象者情報の目的外利用について」の答申後の運用状況についてでありますが、2つの附帯意見を徹底したうえで、身体障害者手帳の等級を確認し、業務を実施しております。
件数につきましては、高齢者等インフルエンザ対象者数32名のうち、13名が受診済、高齢者肺炎球菌ワクチン対象者数21名のうち、3名が受診済との報告を受けております。
3件とも、引き続き個人情報の適正な運用に努めていくとの報告を受けております。
〈10〉 閉会
14時15分終了
〈11〉 補足
会議後、委員からの提案により、今回の諮問事項について再度説明の場を設けることとした。
ダウンロード
*実際の当日配布資料から「恵庭市地域生活支援事業実施要綱」を省略しています。
関連リンク
総務部 総務課
電話 :0123-33-3131(内線:2211・2212)
ファックス :0123-33-3137
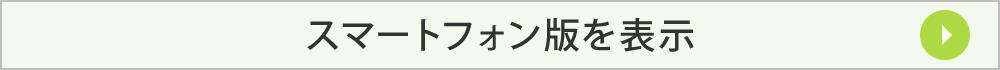








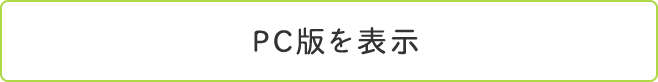

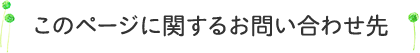
更新日:2019年11月29日