令和6年度 第15回恵庭市小中学生調べる学習コンクール

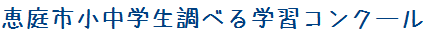
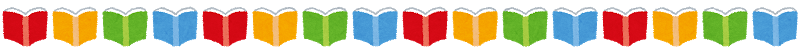
第15回恵庭市小中学生調べる学習コンクールの表彰式が行われました。
令和6年度 第15回恵庭市小中学生調べる学習コンクールは、451名、450作品の応募をいただき、審査の結果、小学生6名、中学生6名、合計12名が入賞され、令和6年11月10日(日曜日)恵庭RBPセンタービル 3階視聴覚室において表彰式を行いました。
表彰式では表彰状等が授与され、受賞者インタビューでは、作品を作るうえで苦労したことや伝えたい思いをお聞きするなど、和やかな雰囲気のなか閉会いたしました。
表彰式の模様が FM e-niwa 『 まちナビ 』で放送されます。
表彰式の模様や市長賞受賞者へのインタビューが、FM e-niwaで放送されます。
・番組名 『 まちナビ 』
令和6年11月12日(火曜日) 17時~18時
(注釈)この番組は翌日(11月13日)早朝5時から再放送も予定されています。
調べる学習コンクール表彰式 講評 審査委員長 恵庭中学校長 工藤 雅人
入賞されたみなさん、誠におめでとうございます。今年度の作品は、小学生154点、中学生296点、合計450点と、非常にたくさんの応募がありました。その中から選ばれた小学生の部6点、中学生の部6点について、感想等を含め講評を述べさせていただきます。
今回入賞した作品は、どれもそれぞれに工夫が凝らされた質の高いものでした。皆さん、図書館を活用し、色々な資料を読み込んで情報を取捨選択してまとめ、実験やフィールドワークなども取り入れて検証する中で、新たな気付きと発見があったと思います。このコンクールに取り組んだ経験は、受賞者一人一人をさらに高めるものであり、恵庭市において大切な取組であると確信したところです。
恵庭市の子ども達の学びの質を向上させるためにも、本コンクールが一層発展し、読書活動の充実及び、主体的に学ぶ力が育まれることを願うとともに、本取組を支えていただいた全ての方々にお礼を申し上げ、審査委員長のまとめとします。ありがとうございました。
令和5年度入賞作品・講評
市長賞
小学生の部
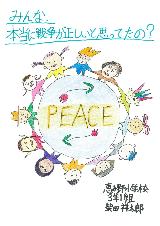
「みんな、本当に戦争が正しいと思ってたの?」
恵み野小学校3年
柴田 祥太郎さん
《講評》
恐竜の図鑑に書かれていた「第二次世界大戦の空襲で化石がこなごなになった」ということから、第二次世界大戦について興味をもち、戦争について調べる中で、当時の人たちが「戦争が正しい」と思っていたことを不思議に感じ調べるなど、動機を深掘りし調べる内容を明確にするとともに、図書館で書籍を用いる他に、映画を見る、戦争の体験者にインタビューをする(その際にも様々な体験活動を取り入れる)、北海道の被爆者会館を訪問するなど、多様な視点を取り入れて作品をまとめています。当時の社会状況を明らかにする中で、そうならざるを得なかったことを理解するとともに、それでも戦争をしていいことにはならないと力強くまとめていることに心を動かされました。
全国コンクール 第28回 図書館を使った調べる学習コンクール 優良賞 受賞
中学生の部
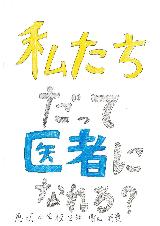
「私たちだって医者になれる?」
恵明中学校2年
雪田 時愛さん
《講評》
将来医者になりたいという思いを強く持っている作者が、「医者」について見つめ直し、「医者」と「差別」を関連付けてまとめるという着眼点が素晴らしいと思います。前半では医者についての理解を深める内容とし、医者は患者を選ぶことができず、全ての患者を平等に扱うことが法律に定められていることを示しています。後半は、日本における差別の歴史といじめ問題について調べ、自分の考えをまとめています。「差別をしないことで医者に近づけるかもしれない」という主張は、医者を目指す人全てに当てはまる言葉であり、まとめにある、「死にたい」と思う人を生み出さない環境をつくることが私たちにできる最も重要なことだという思いを、いつまでも大切に持ち続けてほしいと思います。
全国コンクール 第28回 図書館を使った調べる学習コンクール 佳作 受賞
教育長賞
小学生の部
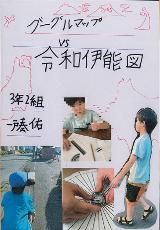
「グーグルマップVS令和伊能図」
恵み野小学校3年
一戸 奏佑さん
《講評》
各都道府県の形に興味を持ち、2年生の時には都道府県の形に着目したジオラマを作りましたが、その中で、歴史上の人物である伊能忠敬を知り、伊能忠敬が地図づくりのために行った測量の方法を調べるとともに、測量の道具を製作し、実際に学校から駅までの道の地図を作成するという力作です。歩数を基に94箇所で測量して実際に地図を作成し、グーグルマップと比較してその成果を明らかにすることは、根気と粘り強さが必要で、地図作りに対する強い意欲を感じました。苦労して作った自分の地図とグーグルマップとのずれを明らかにすることで、普段、当たり前のように使っている地図が、いかに正確で詳しく作られているかについて改めて考えさせられる作品でした。
全国コンクール 第28回 図書館を使った調べる学習コンクール 佳作 受賞
中学生の部

「奥深き塩の世界」
恵明中学校2年
岡田 虹帆さん
《講評》
塩が大好きな作者が、塩の魅力を多くの人に伝えたいとの思いから出発し、塩の種類や特徴、海水塩の作り方等について幅広く調べ、実際に海水塩を制作するなど、塩についての愛情が込められた作品でした。採取の方法の違いや、同じ海水塩でも製法が違う塩について、実際に入手し、味や見た目の違いについて感想が記述されており、こんなに違いがあるのかと感心させられました。また、小樽、苫小牧、えりも、羅臼の海水を採取し、海水塩を自分で作る実験を行い、海水の違いによる味の違いについて考察していますが、考察の着眼点がユニークで引き込まれる内容でした。塩に対する自分の考えがしっかりとあることが調べる内容の深さに繋がっていると思います。
全国コンクール 第28回 図書館を使った調べる学習コンクール 佳作 受賞
学校図書館活動推進協議会長賞
小学生の部

「ミミズのふしぎ」
若草小学校4年
戸塚 大心さん
《講評》
身近にいるミミズについてよく知らないことに気づいたことをきっかけに、ミミズの生態や体の仕組み、種類について図書館の本を中心に調べるとともに、実際に自分の家や学校、などの身近な場所、帯広の親戚の家などの様々な地域や、家の庭、公園、畑など場所や条件を考慮してミミズを見つけ、飼育するなどして、調べたことを確認し、さらに新たな気付きを得るなど、ミミズに対する探究心に溢れる作品です。ミミズに関する書籍が少ない中、少ない資料で終わらせずに、図書館司書に相談し、書庫から専門書を出してもらうなどしたことで、より詳細にミミズの生態について言及できており、種類の特定の難しさにも触れ、自分が探したミミズについてもすべて予想としているところに誠実さを感じました。
全国コンクール 第28回 図書館を使った調べる学習コンクール 佳作 受賞
中学生の部
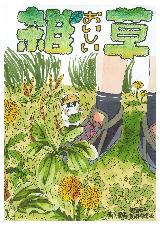
「おいしい雑草」
恵明中学校2年
横川 紗希さん
《講評》
祖母の家で食べた「ふきのとう」や「クレソン」がとてもおいしく、それが道ばたに生えていることに驚きを感じ、身近にある雑草に興味を持って、「食べる」ことを主目的として雑草について調べているところが面白いと思います。主題が明確にあり、見つけた雑草について、植物的な特徴を調べて記述するだけではなく「味の予想」を考え、「苦い」「酸っぱい」などのワードがあることもユニークで興味を引かれます。また食用という視点のため、毒性についてもきちんと調べ注意を促しているところも良いです。さらに、実際にオオバコのおひたしとドクダミ茶をつくって味を確かめるなど、調べるに止めず体験して確認し、実感を持って雑草のおいしさを伝えていることも内容に深みを与えています。
全国コンクール 第28回 図書館を使った調べる学習コンクール 佳作 受賞
審査委員長賞
小学生の部
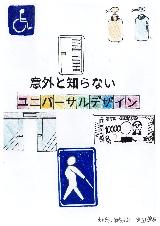
「意外と知らないユニバーサルデザイン」
和光小学校6年
宮田 健成さん
《講評》
SDGsについて学習する中で、「誰もが安心して暮らせる」、「誰ひとり取り残さない」という項目にある「ユニバーサルデザイン」に興味をもち、書籍やWEBサイトを活用して詳しくまとめています。ユニバーサルデザインの定義やバリアフリーとの違いを明確にし、身近にあるお金やシャンプーやボディソープの容器、スイッチ、自動販売機などについて実際に工夫されている部分を確認して紹介するとともに、旅行先で見つけたマークや福祉に関するマークなど、多様な人種や様々な障がいを持つ人にも分かりやすいピクトグラムを生活の中から探すなどして、普段気がつかない場所にも様々な工夫があり役立っていることを実感することができました。
中学生の部
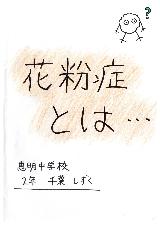
「花粉症とは・・・」
恵明中学校2年
千葉 しずくさん
《講評》
自分が花粉症であり、鼻が詰まって寝苦しく、その対策と解消方法を探すという切実な願いが込められた作品です。花粉症を引き起こす植物がたくさんあること、自然のあるところではなく都会の人の方がなりやすいことなど、自分の予想と違った驚きが率直に記述されているのが良いと思います。対策として、1.花粉を避ける、2.花粉を室内に持ち込まない、3.花粉を除去、4.情報をチェック、5.規則正しい生活、の5点にまとめていましたが、一つの資料から抜き書きするのではなく、多くの資料の中から、自分に必要な情報を取り出し、要点を組み合わせて自分の言葉で記述し、自分の症状改善に役立てるものとしていることに大きな価値があると思います。
奨励賞
小学生の部

「だいすき「おこめ」」
若草小学校1年
戸塚 凰心さん
《講評》
お米が大好きな気持ちが真っ直ぐに伝わってくる作品でした。ごはんが大好きで、田んぼのオーナーとなって田植えをし、お米を作ったことをきっかけにお米について詳しく調べています。お米の構造と種類や、お米作りの手順と田んぼの管理や田植えなど、お米作りに関して自分が体験した感想を入れて生き生きと描写しているところが素晴らしいと思います。また、実際にお米を炊飯器とお鍋で炊く体験活動を行い、それぞれを食べ比べて「炊飯器はもちもち」、「お鍋は粒がしっかりしている」と分析し、それぞれの良さについてまとめ、これからもお米を大切においしく食べたいとまとめています。お米を大切にするという素朴で率直な感想はとても大切な事だと思いました。
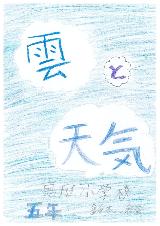
「雲と天気」
恵庭小学校5年
鈴木 彩愛さん
《講評》
理科の授業で習った「天気の変化」と「台風接近」から天気について興味をもつなど、学校で学習した内容を基に発展させているところが素晴らしく、学びを深めるということはこうしたことなのだと思います。学習内容から疑問に思った「空や夕焼けの色」、「降水確率について」、「台風の目について」は、自身が描いたイラストと合わせてとても分かりやすい内容でした。また、雲をつくる実験を行い、調べたとおりに行った作業で実際に雲ができた様子では、雲が発生したことを見て確認することができた驚きがよく表現されていました。こうして調べたことを基に、夏休みに実際に自分が見た雲を撮影して紹介し、学んだことを生活に反映させていることも価値のあることだと思いました。
中学生の部
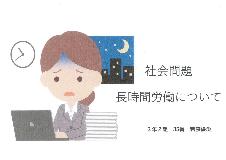
「社会問題 長時間労働について」
恵庭中学校3年
若狭 優愛さん
《講評》
社会問題に関心がある作者が、最近報道やニュースでも社会問題として取りあげられている「長時間労働」について真っ直ぐに向き合い、中学生らしい感性でまとめられています。大人は問題と思っていても仕方がないこととしてしまいがちな部分についても、たくさんの資料の中から情報を精査し、冷静に事実を積み上げ客観的に分析するなど、とても説得力のある内容となっています。多くのビジネス用語が用いられていますが、難しい用語についてよく理解し適切に使用さてれいることにも驚かされました。調べる活動を通して長時間労働が働く人の健康への影響や生活の質の低下を招くことに気づき、自分の将来を見越し働き方や生活に関する意識を変える契機としていることは素晴らしいと思います。
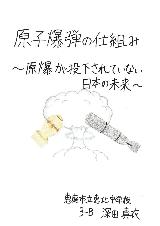
「原子爆弾の仕組み
~原爆が投下されていない日本の未来~」
恵北中学校3年
深田 真衣さん
《講評》
『原子爆弾の仕組み ~原爆が投下されていない日本の未来~』
広島と長崎に投下された原子爆弾がウランで作られたものとプトニウムで作られたものという違いがあることに疑問をもち、漠然とただ恐ろしい兵器として認識するのではなく、その原理と作られた歴史的背景を踏まえ、二度と悲劇を繰り返さないために自分たちにできることを考えるという視点は、今最も必要なことだと思います。原子爆弾の仕組みと、その開発の歴史について詳細に調べてありますが、そこに添えられている自分で描いた緻密なイラストが説得力を増しています。核兵器を実践に投入するまでの様々な葛藤は登場人物の描写もあり、とてもスリリングで、どこかで原爆の投下を止めることができたかもしれないと思わせる優れた内容でした。
教育委員会教育部 読書推進課
電話 :0123-36-1545
ファックス :0123-37-2184
お問い合わせはこちら
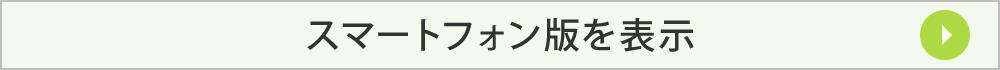








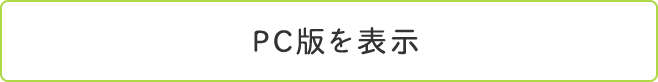

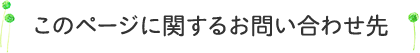
更新日:2025年03月24日