むし歯予防のためのフッ化物洗口の実施について
小学校におけるフッ化物洗口の実施
恵庭市では、北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例と恵庭市健康づくり計画(後期計画)に基づき、子ども達のむし歯を予防し、健康な歯の育成のため、学校歯科医の指導のもと平成25年から小学生を対象に「フッ化物洗口」を実施しています。(平成25年7月から4~6年生、同年11月から1~3年生を対象に実施しています。)
また、恵庭市では、洗口事業を開始した平成25年度から、児童一人当たりのむし歯本数は減少傾向にあります。(令和2年度~令和5年度は新型コロナウイルス感染予防のため洗口事業を中止、令和6年度から再開)
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
令和元年度 |
| 0.75本 | 0.59本 | 0.54本 | 0.50本 | 0.42本 |

フッ化物洗口の説明動画
フッ化物洗口Q&A
| Q | A | |
|---|---|---|
| 1 | フッ素とはどのようなものですか |
フッ素(F)は、自然界に広く分布し、私たちが毎日飲んでいる水道水や飲食品(海産物、肉、野菜、お茶、ビールなど)にも含まれている自然環境物質です。また、私たちの体の骨や歯、唾液、血液、内臓などにも存在しています。ただしフッ素は大変反応性が強い元素であるため、自然界では必ず他の何らかの元素と結合した「フッ化物」として存在しています。そして、むし歯予防にはフッ化ナトリウムなどの無機フッ素化合物が使用されます。 |
| 2 | PFAS(ピーファス)という有機フッ素化合物が問題となっていますが、フッ化物洗口液とは違いますか。 |
むし歯予防のために使用するフッ素は「無機フッ素化合物」であり、自然界には存在せず人工的に合成された有機フッ素化合物であるPFASとは全く異なる物質です。 PFASは、発がん性やワクチンによる免疫効果の低下などの影響がありますが、フッ化物洗口で使用する洗口液は無機フッ素化合物のため、適量摂取することでの有害性はなく、むし歯予防や骨粗鬆症の予防効果があります(市販の歯磨き粉にも入っています)。 上記と似た例として、塩素(Cl)の入った有機塩素化合物であるクロロホルム(CHCl₃)等のトリハロメタンは、肝臓障害、腎臓障害、発がん性等を有しますが、ナトリウムと結合した無機塩素化合物である食塩(NaCl)は日常に必要不可欠なものとなっていることが挙げられます。 |
| Q | A | |
|---|---|---|
| 1 | なぜフッ化物はむし歯を防ぐのですか。 |
フッ化物には、歯質を強化し、再石灰化を促進し、むし歯菌の活動を抑制する作用があります。(注意)歯質の強化:エナメル質の結晶を強くし、むし歯になりにくくします。(注意)再石灰化の促進:むし歯になりかかった歯の表面を修復し、進行を抑えます。(注意)むし歯菌の活動の抑制:むし歯菌が歯を溶かす活動を抑えます。 |
| 2 | フッ化物洗口を開始して、どのくらいでむし歯予防の効果があらわれますか。 |
効果が現れてくるのは、開始してから2~3年後からです。特に、上の前歯はむし歯予防の効果が現れやすいとされています。 |
| フッ化物洗口を実施することで、どのくらいむし歯が減っているのですか。 |
平均で40~80%のむし歯が減ることや、多数歯(4本以上)にわたるむし歯のある子どもの割合が減ることが報告されています。 |
|
| 4 | 子どもの頃にフッ化物洗口を実施すれば、大人になってもむし歯予防の効果はありますか。 |
洗口が終了してから大人になってもむし歯予防の効果は持続します。 |
| Q | A | |
|---|---|---|
| 1 | 洗口液を誤って飲み込んだ場合、身体に害を及ぼすことはありますか。また、歯のフッ素症になりませんか? |
1回分を飲み込んでも安全です。 フッ化物の急性中毒量は、体重1キログラムあたり2ミリグラムとされています。例えば、体重30キログラムの小学生の場合、急性中毒量は60ミリグラムであるのに対し、1回分の洗口液10ミリリットルに含まれるフッ化物量は9ミリグラムであるので、6~7人分以上を一度に飲み込まない限り、急性中毒量には達しません。 また、フッ化物の慢性中毒として歯のフッ素症や骨硬化症がありますが、使用するフッ化物の量や適用期間から、フッ化物洗口で発生することはありません。 |
| 2 | 病気によっては、フッ化物洗口を実施してはいけない場合がありますか。 |
特にありません。 フッ化物洗口は、うがいが適切に行われる限り、身体が弱い人や障がいをもっている人が特別にフッ化物の影響を受けやすいということはありません。 またその他、「服薬中」であっても、フッ化物洗口を実施することができます。フッ化物洗口により口の中に残るフッ化物量は、毎日飲食物から摂取するフッ化物量以下か多くても同程度のため、服薬中でも問題はありません。 |
| 3 | フッ化物でアレルギー反応を起こす人はいますか。 |
フッ化物そのものがアレルギーの原因となることはありません。 これまでにむし歯予防に利用するフッ化物洗口に含まれるフッ化物そのものでアレルギー反応を生じたという信頼に足る報告はありません。また、専門機関や学会においてもフッ化物とアレルギーの関係は科学的に否定されています。 |
| 4 | 口の中にキズや口内炎があるときに、フッ化物洗口を行っても大丈夫ですか。 |
フッ化物洗口液は刺激性のものではないので、口の中のキズや口内炎に影響することはありません。ただし、水がしみたり、口をブクブク動かすことで口の中のキズや口内炎に我慢できない痛みが出るようであれば、その間は無理して行うことはありません。 |
| 5 | フッ化物洗口には劇薬を用いると聞きましたが、大丈夫ですか。 |
むし歯予防のために調製されたフッ化物洗口液は劇薬ではありません。 フッ化物洗口には主にフッ化ナトリウム水溶液が使われています。市販の医薬品であるミラノールやオラブリスは医薬品医療機器等法施行規則に基づき劇薬扱いとなり、フッ化ナトリウム試薬も粉末では劇薬に相当しますが、洗口に用いられる溶液は、フッ化物濃度が0.09%であることから、同規則にある劇薬指定除外規定のフッ化物濃度1%以下に該当となり、劇薬指定から除外されます。なお、フッ化物洗口液の作成は薬剤師が行い学校に納品しているため、学校で劇薬を取り扱うこともありません。 |
| 6 | フッ化物洗口で事故が起こったことはないですか。 |
日本で本格的にフッ化物洗口が実施されて50数年が経過していますが、正しい方法で行われるフッ化物洗口での事故報告は見当たりません。 |
| 7 | フッ化物を乳歯の段階で使い続けると、永久歯が出てくるのに邪魔をする可能性はないですか。 |
そのようなことはありません。 フッ化物で歯質が丈夫になっても、永久歯の形成とともに乳歯は脱落していきます。むしろきちんとした予防がなされず、乳歯がひどいむし歯になってしまうと、永久歯の形成や歯並びに悪い影響を与えます。生涯を通じた歯の健康のため、フッ化物によるむし歯予防は、永久歯はもちろん、乳歯についても有効といえます。 |
| 8 | フッ化物洗口で口の中に入ったフッ化物は、身体に蓄積されますか。 |
フッ化物は体を構成している元素のひとつです。また、お茶や水、魚介類、肉類、根菜類や海藻類など多くの食べ物の中にもフッ化物は含まれています。フッ化物は体にとって必要なものなので、必要な量は体に蓄積されますが、必要のない分は尿や便、一部は汗、涙、唾液などから排泄されます。 |
| 9 | フッ化物洗口で何か問題が起きたら、責任はどこにありますか。 |
フッ化物洗口の安全性は充分に確立しているので、定められた実施手順にしたがって、フッ化物洗口を実施すれば有害作用が起こることはありません。仮に有害作用と思われることが起こった場合は、他の一般的な公衆衛生事業と同様、国や都道府県及び実施主体である市町村のそれぞれの立場に応じた責任で対応することになります。 |
(注意)参考資料
・北海道フッ化物洗口ガイドブック【実践編】
北海道・北海道教育委員会・北海道歯科医師会・北海道歯科衛生士会
発行(第4版:H31.3)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/f-senkou.html
・フッ化物洗口Q&A
茨城県・公益社団法人茨城県歯科医師会
https://www.ibasikai.or.jp/wp-content/uploads/2022/05/Fluoride_mouth_rinse_QA.pdf
・PFASと歯科で使用する無機フッ素化合物について
公益社団法人日本小児歯科学会小児保健委員会
ダウンロード
教育委員会教育部 教育総務課
電話 :0123-33-3131(内線:1611)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
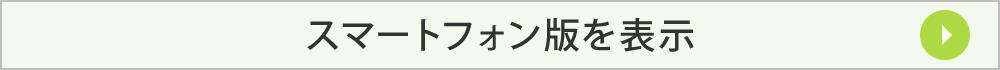








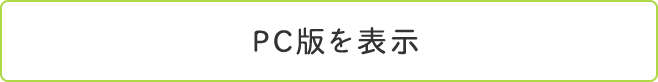

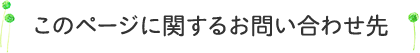
更新日:2025年03月05日