常設展示案内
常設展示室へようこそ
常設展示室は6つのテーマで構成されています。主な展示物は次のとおりです。
第1部 恵庭の大地
≪主な資料:動物の剥製、画像検索システム≫
約4万年前、支笏火山が大爆発を起こし、大量の火山灰が降り積もって恵庭の大地が形づくられました。
長い年月の後、豊かな緑におおわれ、さまざまな動物たちが息づく恵庭の大地となりました。

動物・野鳥の剥製

画像検索システム
第2部 先住の人々
≪主な資料:柏木B遺跡周堤墓模型、北海道式古墳模型≫
恵庭に人が住み始めたのは約7千年前。
縄文文化、続縄文文化、擦文文化と幾千年もの間続いた人びとの生活の跡が多数発見されています。

遺跡発掘調査出土品~縄文土器

柏木B遺跡周堤墓(しゅうていぼ)模型

恵庭の縄文文化

発掘現場のデジタルフォトフレーム
埋蔵文化財コーナーでは、土器展示棚の改修、模型のガラスや手すりを撤去し、これまでより展示物が見やすくなりました。展示資料には、最新の発掘成果を多く取り入れています。また、発掘現場の様子を撮影した写真をデジタルフォトフレームで公開しています。
第3部 アイヌモシリ
≪主な資料:丸木舟、狩猟用具、祭壇≫
擦文文化の次にすべてのものが神であり、人間は神の恵みを受けて生活するという考えを持ったアイヌ文化が続きます。
(注意)アイヌモシリとは、アイヌ語で「人間の静かなる大地」を意味する言葉。

ヌササン~いろいろな神を祭ってある祭壇

丸木舟

北海道地図 「蝦夷図」

アイヌ民族資料 漆器
江戸時代の探検家 間宮林蔵が測量を行って作成された北海道地図 「蝦夷図」が加わり、当時の恵庭周辺の様子を図上で確認することができます。
第4部 大地をひらく
≪主な資料:明治期の文書、教科書≫
本格的な開拓は明治19年から集団入植の人びとによって進められてきました。
未開の地での開墾は厳しい自然や災害との闘いでした。
やがて農作物が収穫され、酪農も行われるようになりました。

明治コーナー

明治時代の金庫
明治コーナーでは、解説パネルが見やすくなりました。
第5部 恵庭村の誕生
≪主な資料:農林業用具、生活用具≫
明治39年、恵庭村が誕生しました。大正15年、鉄道の開通を契機に産業が発展し、人口も増えてきましたが世の中は太平洋戦争へと突入していきました。

いろり全景

生活用具

農林業用具

消防ポンプ
いろり部分を1軒の家に見立て、見学できるスペースを広くしました。 また、農業や林業資料を産業ステージに集め、解説文や資料との距離が近くなり、見やすくなりました。
第6部 戦後のくらし
≪主な資料:昭和30~40年代の生活用具≫
昭和20年、戦争が終わり、復興の時代を迎えます。
昭和26年、町制が施行され、高度経済成長期の最中、 昭和45年、恵庭市が誕生しました。

昭和30年代の生活用具

インクライン模型

昭和40年代の生活用具

収蔵写真をデジタル画像で閲覧できます
設定年代を昭和40年代まで引き上げ、新たに当時の生活用具を加えました。また、郷土資料館収蔵の写真資料約1200点をデジタル画像で閲覧することができるようになりました。
昔の道具体験コーナー(エントランスホール)

火おこし(まいぎり式、きりもみ式)

電話(ダイヤル式、プッシュ式)

魚釣り体験
教育委員会教育部 郷土資料館
電話 :0123-37-1288
ファックス :0123-37-1288
お問い合わせはこちら
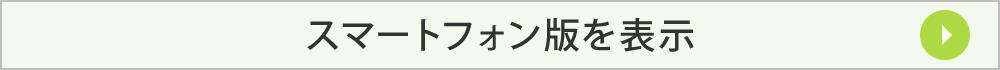








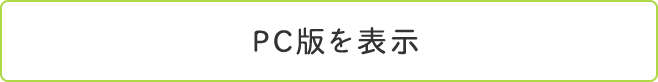

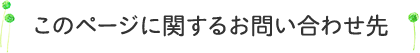
更新日:2023年11月27日