【高齢者補聴器利用促進モデル事業】よくある質問
【高齢者補聴器利用促進モデル事業】よくある質問
Q1:付属品も助成の対象となりますか。
A1:助成の対象となる費用は、補聴器の購入費用及び補聴器相談医の意見書作成費用となります。補聴器の価格に含まれているレシーバーやブラシなどは対象となりますが、別売りの充電器やバッテリー、電池等の付属品は対象となりません。
Q2:インターネットで購入した補聴器は対象となりますか。
A2:補聴器をより効果的に活用していただくために販売店にてフィッティング(調整)をしていただく必要がありますので、通信販売は助成の対象外となります。ただし、実店舗へ行くことが難しい場合などで、出張サービスにてフィッティングを行える場合は助成対象といたします。
Q3:集音器は対象になりますか。
A3:対象となる機器は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で「管理医療機器」に指定されている「補聴器」のみとなります。集音器は対象としていません。
Q4:助成は何回受けることができますか。
A4:多くの方に事業を活用いただくため、お一人一回までとなります。
Q5:診断を受けるのは補聴器相談医でなければならないですか。
A5:難聴は、「聞こえの状態(聞こえない音域)」を医学的に正確に把握し、聞こえの状態に適した補聴器を処方しなければ、かえって聞こえを悪化させてしまうことがあります。
このため聴覚障害の専門知識を有する補聴器相談医を受診していただく必要があります。
Q6:医師の診断の結果、補聴器が必要と認められなかったが、聞こえにくさを感じるため、補聴器を購入したいのですが助成対象となりますか。
A6:補聴器は医療機器であり、適切な処方に基づかない使用は、かえって症状を悪化させる恐れがあります。そのため、医師の診断により必要と認められなかった場合は、助成対象とはなりません。なお、今回、助成対象とならなくとも、聞こえについて課題をお感じの場合は、引き続き補聴器相談医へご相談ください。
Q7:なぜ聴力検査やフィッティング(調整)が必要なのですか。
A7:補聴器は精密機器ですので、性能を正しく発揮するためには、技術者による使用者の耳の状態に合わせた細かい調整が必要になります。そのため、補聴器相談医での受診、補聴器販売店での聴力検査及び調整を要件としています。
Q8:補聴器販売店の見積書に様式はありますか。
A8:様式は定めていませんが、補聴器であること(品番・型番の記載)、価格、見積年月日がわかるような記載が必要です。
例)令和7年4月1日
補聴器(○○社製、型番●-●)、△△円
Q9:片耳だけの購入も助成対象となりますか。
A9:片耳、両耳を問わず対象としています。
Q10:補聴器を既に使っています。修理は対象になりますか。
A10:修理は対象になりませんが、今までお使いの方が新たに補聴器相談医に必要性を認められて、買い替える場合は対象となります。
Q11:アンケートは必ず回答しなければならないですか
A11:アンケートは、事業のあり方の検討材料及び助成の要件としているため、必ずご回答をいただきます。
(注意)使用前アンケートは助成申請時、使用後アンケートは助成後3か月を目安にご回答いただきます。使用後アンケートはご自宅に郵送いたします。
Q12:身体障害者手帳(聴力)を持っていますが、この制度を利用できますか。
A12:聴力レベルが身体障害者手帳交付対象となる方は、補装具支給制度の対象となるので、この制度の対象とはなりません。
詳しくは保健福祉部障がい福祉課(電話:0123-33-3131(内線1215))までお問合せください。
Q13 :補聴器購入費用に対して医療費控除は受けられますか。
A13 :補聴器相談医が在籍する医療機関を受診し、認定補聴器専門店で補聴器を購入するなど、一定の要件を満たすと医療費控除の対象となります。詳しくはお近くの税務署にご確認ください。(電話相談センター:0570-00-5901)
保健福祉部 介護福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1209・1224)
ファックス :0123-39-2715
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
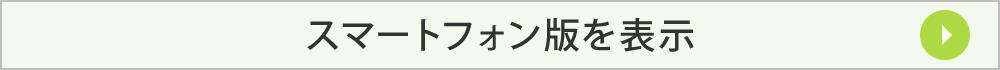








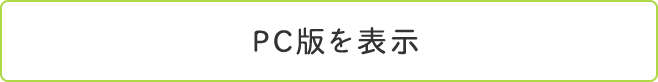

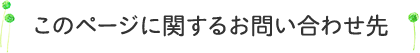
更新日:2025年03月27日